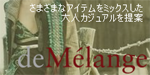| << NEXT | Main | BACK >> |
2009-04-14 Tue
先週はいい~お天気が続いていました。
自宅前は、白の八重桜がホンワリ丸く、綺麗に咲いています。
こんなに、ポカポカ天気が良いと、猫も日陰にこもって気持ちよさそ~に昼寝をしています。
先週は、そんな良いお天気の中、「赤ちゃん」が生まれた友人Rの家を訪ねました。
以前、このブログに書いた、アメリカ人の旦那さんを持つ友人です。
昨年会ったときは、6ヶ月でお腹が大きい状況でしたが無事出産
男の子のBaby-ネイサンちゃん
小っちゃくて可愛い
まだまだ小さいので、どっちに似ているのか判断しにくい。
しかしながら、逆子だったため出産は「帝王切開」となったようです。
「出産後がホント痛くて..。くしゃみも咳きも笑うのも、痛くって我慢してるのよ~。もう絶対に普通に出てくる分娩の方がいい。」とこぼしていました。
やや前かがみに腰を曲げつつ歩く友人の姿を見ていると、私の腹部まで痛くなってくる..。
そういえば、華僑の財閥と結婚した知合い女性が言うには、中国(資産家)の家では出産は殆どが帝王切開らしい。
彼女も二人の子供を出産しているが、二人とも日にちを前もって決め、帝王切開で産んだそうだ。
生年月日による「運勢」についてとっても気にするらしく、子供の運気を上げるために、出産日を先回りして決めるため、そうなるのだそうだ。
しばらくすると、Rの家族の皆さん(彼女の母、ご主人の母、ご主人)が外出から戻ってきました。
新宿の伊勢丹で買物をしてきたようです。ご主人のお母さんの東京での観光も兼ねておそらく「伊勢丹」を選んだのでしょう。
Rもご主人も伊勢丹の地下食材売り場で、フランスのチーズの専門店が撤退していたことをことのほか残念がっていました。
多分「マリーアンヌ・カンタン」のことだと思うけれど、日本ではもうショップはないのかもしれない。新宿伊勢丹って、すっごくいい点でもあり悪い点でもあるけど、入れ替えが多くて早い。
東京では世界一美味しい「レストラン」は数多くあれど、数多くの美味しいチーズの種類をそろえているお店はないようです。
昔と比べれば、ワインの流行と共にチーズの専門店も出来て、店頭にならぶチーズの種類ははるかに増えましたが、やっぱり日常的に様々な種類のチーズを食べるってことが、日本人の食文化にはまだまだないのではないでしょうか。
案外、数年前の方が食料品店のピーコックに並んでいるチーズの種類も多かったように感じます。
20代の頃、旅行でスイス人の友人宅に泊まり、土曜日の朝ごはんを用意してもらったところ、いろんなチーズとハムとパンが数多く並んでいて(品評会のような)、なんと沢山の種類のチーズとハム!とビックリしたのを憶えています。私の驚いた表情を見た友人は、「これって典型的なスイス人の週末の朝の食卓なのよ。」と教えてくれました。
余談ですがRの自宅マンションは、都心のど真ん中にありながら、ため息がでるほど私好みの風情と場所にあり、遊びに行くとそれだけで癒されるような感じです。窓から見える景色も、東京タワーと高いビルが見えますが、マンションは坂の上にある高台なので、たっぷりと緑の木立を見下ろすようになっていて、とっても落ち着く静かな場所です。
マンションの門を過ぎると、エントランスまで続く長~いアプローチが、樹齢の長そうな木立に囲まれてまるで、夜になって歩道を照明が照らすと、バリの高級リゾートに来たような気分になります。(いいわぁ~、金額が高すぎて無理だけど、都心ど真ん中でもここだったら住みたい。
両方のママがいると、赤ちゃんを抱っこしてくれる「手」が沢山あります。
まずは仕事を早く終えてきたご主人が、早口の英語と日本語のちゃんぽんで何やら呟きながら赤ちゃんを抱っこ。
そのうち、Rのママが抱っこ、しばらくするとご主人のママが抱っこ。
赤ちゃんがいるだけで、場が明るくなり和みます。
両家にとっては、初孫らしく、盛り上がる気持ちは分かるなぁ...。
私も初めて生まれた「甥」を見たとき、ものすっごく感動して盛り上がった。
な~んて、可愛いんだろう。
さて、Rはしばらく日本にいて、その後はサンフランシスコに移動する予定。
今後、彼女が抱える子育ての課題の一つは言語となってくる。
両国の祖母とコミュニケーションが取れる子供になって欲しいというのがRの願いでもある。
現地のプレップスクールに入学させれば、やはり英語が主体となっていくことは間違いない。
日本語学校に通わせる家も多いらしいが、それでも、文法的におかしいとか、強い訛りのある日本語しか話せない子も珍しくないらしい。
ともかくも、友人が高齢出産を無事切り抜け、可愛いBaByを生んだことは「すごい」こと。
先日もある知合いの女性から、やはり同じく高齢出産で生まれた、可愛い男の子の赤ちゃんの写真とお便りを受け取りました。
女性の皆さん、えらい。
by bandoh
徒然なるままに : 11:47 : comments (x) : trackback (x)
2009-04-12 Sun
「ヒューマン・ライツ・ウォッチ」(以下HRW)の代表のケネス・ロス氏のセミナーを聴きにいく。
「HRW」は昨年、「ノーベル平和賞」を受賞した世界最大級の国際人権に関わるNGOである。
このセミナー
「ビジネスマンと人権問題は無縁か?」というタイトルで、
マネックス・グループの松本社長が問題を提議するという形式で行われた。
会場には約100名ほどの人が集まっていた。
ケネス・ロス氏
正直言うと、案内が来るまで、「人権問題」について日頃から、私自身はそんなに考えているわけではなかった。
特に国内の人権問題については、殆ど日々考える機会は薄いと思う。
ただし、アフリカやアジアの子供達の悲惨な惨状を見るにつけ、心を痛めることがあり、何か自分に出来ることはないかと、ここ数年前からスリランカの子供の教育支援に関して、微力ではあるが援助をしている。
なので、国際的な人権問題の改善について、組織の規模以上に、飛躍的な成功を収め貢献している人権NGOである「HRW」の代表が直接話す内容を聞きたいと思った。いつも、「本物に触れる」という機会は貴重である。
ケネス・ロス氏が語る内容から、
「HRW」が、NGOながら人権問題の改善について、小さな貢献というよりは、一国の政府を動かすまでの、大きな影響力を発揮するまでに至るには、「鍵となる3つの要素と"良循環"」があることが分かった。
ビジネス・モデルというと御幣があるが、大変上手く機能している「システム」だと思う。
★1つ目は「恥をかかせる」プレッシャー1
調査する国に弁護士、ジャーナリスト、学術関係者など「専門家」を調査員として派遣し、徹底的にそこで何が起きているのかを調べる。人権侵害を受けた「被害者」や、被害を目撃した人などから直接話しを聞く、政府と話し合うなどして、公正かつ正確に「証拠」を探すのである。そしてそれらをきちんと報告書としてまとめあげ、プレスを集めて発表し、記事として書かせる。(ちなみにHRWの報告書は、政府よりも信頼性が高いと認識されているらしい。)
このことにより、行われている「人権侵害」について、スポットライトをあて陽のもとに曝し、政府に「恥」をかかせる。
そうやって、独裁者やその政府にプレッシャーをかけるわけである。
★2つ目は外交的・経済的な施策を打つ:プレッシャー2
その国に影響力を持つ援助国の「政府」に対して、「援助」を打ち切るように交渉する。
この事で当事国の独裁者や政府に、人権侵害が「高くつく」ようになるような流れを作る。
★3つ目は国際裁判所にて訴訟を起こす:プレッシャー3
この手法は、最悪のケースとなるが、スーダンの元大統領のように、国際的な形で裁かれるよう手続きを取り、実際に法廷に出廷させるまでの道作りを行う。
この3つのことを、継続して、「繰り返し繰り返し行っている」ことが成功の秘訣らしい。
つまり、優秀な「専門家」を雇って徹底した調査を行う→政府の発表よりも高い信頼性を持つ、公正で正確な「人権侵害の報告書」によって各国プレスを動かす→引いては政府を動かす→実際に人権侵害を改善していくという結果を出し→国際的な問題に意識の高いビジネス・マンやセレブから資金援助を受ける→優秀な専門家を雇う資金を調達→調査を行う.....
という「良循環」を繰り返して、今の影響力を築き上げたそうだ。
(ハリウッドのセレブも資金援助している人が多い。)
なるほど....
しかしながら、そうはいっても、この流れを作っていくためには、相当の知識とノウハウ・スキルが必要になると思う。
例えば...
・調査能力
・その国の文化や経済・政治、人権などに関する専門知識
・複数の外国語をこなす言語力
・報告書を作成する能力
・プレスを集めて発表するプレゼン能力
・政府と交渉する交渉力
・自分ひとりで活動し完結するための自己管理能力
・危険を事前に察知したり、リスクを計算し回避できる能力
結果としてものすご~く、濃い経験とスキルが必要、いや結果として身につけることになるのであろう....。(すごい)
おそらく「HRW」はそうやって、一人の学者だけでは決して成しえないような、かなりの知識と情報が着実に共有され、高度な政治への影響力を持つ団体へと発展していったのだと想像する。
そこで働く人にとっては「胆力」とか「強い使命感」を持っていないのと、決して続かない"大変で難儀な仕事"だと思う。
がしかし、その職に対する人気は相当高いようで、先日もとあるアジアの国で募集を行った際、1つのポストに300名の募集があったそう。
ケネス・ロス氏は、セミナーで知的にタンタンと語っていたが、その話しの分かりやすさと、静かなるコミットメントが強く印象に残った。
人権擁護団体というと、私の中ではちょっとした「ネガティブ・イメージ」が団体によってはあるのだが
ロス氏は押し付けたり、驕っているようなそぶりも見せないので、嫌味がない。誠実で信頼できる人という感じがする。彼の能力とそのパーソナリティが、これまで支援者からの賛同を集める要素の一つにもなっているのだろうと思う。
彼は、ロースクールを卒業後、NYにある大手弁護士事務所に就職したのだが、仕事に心から満足できず、その後犯罪を扱う検事となったが、そこでも心から満足できず、「HRW」と出会いようやく「ここだ」と思ったそうだ。自分が本当にやりがいを感じられるのは「人権問題」だと。その後、彼は現在まで約21年間、「HRW」で活動することになる。
ケネス・ロスさんは言う。
「この仕事は信念を持ってできる仕事」であり「違いを起こす仕事」である。そして「毎日課題がある」と。
その一言一言に、静かではあるが、自分自身が「信じる価値を生きる」人が持つ強い「コミット」を感じた。
ケネス・ロスさんを始め、安藤忠雄さん、松原泰道さん、ムハメド・ユヌスさん、皆、一様に分野は違えど、素晴しいリーダーだと思う。
こういった素晴しいリーダーと直接会うことが出来て、話しを聞くことができるのは大変ありがたいことである。
またそういったリーダーの共通点としては、彼等の話しを聞くと、「心の中に勇気が湧いてくる」ことであろう。
何かしら与えられた気持ちになるのである。
皆一様にそういったポジティブな影響力を持ち、「周りの人にエネルギーを与える」人達だと思う。
これは、企業の経営者やリーダー層にも必須の条件だと思う。
一緒にいてエネルギーが縮むリーダーの下にいたら、この不景気の時代、創造性も発揮できず絶対に成果が出るわけが無い。
やはり、一人一人が自分の「価値」を知り、前向きに生きることが大事であると感じた。
さて、ケネス・ロス氏が東京でセミナーを開いたのは、私たち日本人(特に経済や政治のリーダー)が、もっと国際的な視野に立ち、「人権問題」に意識を持って行動を起こすことにあると思う。(世界同時不況で、一番のスポンサーである欧米金融系のビジネスマンからの寄付金も減っていると思うし。)
しかし、懸念が....
「商人国家」である"ジャパン"は、商売上のお客様である諸外国(北米や中国、ヨーロッパなど)や原油産出国等に、言いたいことを思い切って言えないのではないだろうか....。
また、戦争で近隣のアジア諸国を侵略したという「加害者意識」もあり、アジア諸国の中で起きている人権問題について、明確に異議を唱え行動を起こすことは、"微妙"といおうか..、躊躇する傾向があるのではないだろうか。
「チベット問題」や、「中国における人権問題や環境汚染」など、日本政府の対応を見ていて歯がゆい思いをすることが多い。
そう考えると、ある意味、「HRW」が東京に事務所を開き、日本の"プレス"や"政府"に対して、積極的に働きかけてくれる(圧力?)ことは、歓迎すべきなのかもしれない。
私たちの国の世論がもっと成熟し、政府が近隣諸国に対して経済支援以外にも貢献し、国際的にもきちんとした「リーダーシップ」を取って行く、という意味において「HRW東京事務所」がプラスに機能して欲しい。そう思うと、これはありがたい話しなのかもしれない。
結論。
「私も"HRW"に寄付をしよう!」
by bandoh
コーチング : 14:32 : comments (x) : trackback (x)
2009-04-08 Wed
東京は桜が多い。
以前、「京都の桜」を楽しみに京都へ行ったことがあるのだが、想像していたよりも桜が少なくかつ人が多くガッカリした記憶がある。
そりゃ~、「醍醐寺」のソメイヨシノとかシダレザクラは樹齢も長く美しい。
「貴婦人のようだわ~
東京の場合、桜の見所がアチコチに点在していて、その量が多いと思う。
日曜日、知人の息子さんの告別式に参列した帰りに、車の中から「目黒川沿いの桜」を見たが、川の両岸に互いにもたれかかるようにして、みっちりと咲いた満開の姿を見せている桜はうっとりするほど綺麗だった。
また、渋谷にさしかかると、渋谷の桜丘の坂を上がる両脇の桜トンネル、これも美しい。白金近辺の桜も綺麗だった。
「千鳥ケ淵」には1000本のソメイヨシノとヤマザクラがあり、夜になってお堀沿いにライトアップされる桜は幻想的で圧巻。

その他、「新宿御苑」の桜、「砧公園」の桜、「上野公園」の桜など、見所が沢山ある。
もしかしたら徳川幕府の頃に取られた政策、江戸文化からの続きなのかもしれない...。
ちなみに、こちらは自宅近くにある桜トンネルの一つ
これは自宅前に咲く桜
この時期になると、ハラハラと風に乗って桜の花びらが落ちてくる。
夜になると、この桜からポッカリとのぞく月がまた風情があり、
家までの帰り道を楽しいものにしてくれます。
そういえば、今月は明日が「満月」です。
願いごとをしましょう。
毎年、満開の桜を見ると心が浮き立ち季節の変化をはっきりと自覚し、何やら仕事へのエネルギーが高まってくるから不思議。
今晩は、六本木でマネックスの松本社長の「ビジネスと人権問題」に関するセミナーがあります。
内容を期待しつつ.....。
by bandoh
徒然なるままに : 12:29 : comments (x) : trackback (x)
2009-03-30 Mon
今年も「お花見」の時期がやってきました。
考えてみると、私が世田谷で最初にお花見を始めたのは、1993年頃だったような気がします。
それ以来、近所にある「砧公園」で度々行うことに。
まずは皆で小田急の「千歳船橋駅」で待合せ。
また、その待ち合わせは、「12時から1時の間に集合」という、普通の人が聞いたら「何それ?
当時の企画者の一人、友人キヤロライン・ブリエが大体そんな感じだったせいもあります。
これは、93年当時の写真です。古い~。
下にしゃがんでいるのが私とキヤロライン。(この集合写真は今回のお花見に参加している友人H嬢が撮影)

その後、キヤロラインが日本を去り、私が97年に会社を辞めて独立したりでバタバタとしていた時期は、近所での「お花見」企画を中断していましたが、
近所に自宅を購入し、ラッキーなことに自宅前には桜の木があることから
そう!だから、長い人だと一緒にブランクはあれど、93年からお花見を楽しんでいることになります。
(光陰矢の如し。時の流れは早い....
さて、このお花見の自宅パーティ、実は最も大変なのが「事前準備」
15-20名位の人が来るとなると、お食事の内容、ボリューム等、普通のようには行きません。
(よくホームパーティされる方なら、ご存知ですよね)
だから毎年、友人が"助っ人"として、「料理」と「買出し」を担当してくれています。
助っ人OさんNさんとOさんの長女のアキちゃん
パーティは14時30分からスタートし大体24時から0時までエンエンと続きますが、その間ずっと何かしら食事を作って出してくれます。(涙&感謝)
助っ人Sさん
フランスパン5本を一口サイズ用に切り刻んでいます。
Sさん、日頃は某企業のこわもて部長さんですから、部下を切り刻んでも、こんなにフランスパン刻む機会少ないと思います。ハハハ..
何となく始められそうな感じになってきています。
(今日は寒いので残念なら表に出ることはちょっと出来そうにありません。)
アボカドとトマト、カレー味のディップ Oさん作
フランスパンと一緒に
マグロのタルタル 醤油とバルサミコのソース Nさん作
グレープフルーツとオレンジのリキュール&ミント Nさん作
アキちゃんとNさん 彩りの綺麗なお食事を作ります。
アキちゃんの助っ人ぶりが見事なのは、父Oさんの教育????
第1陣の皆様にもまずはお食事を楽しんでいただいて
厨房は元気。人の出入りも多い...。ここに来ればテーブルに出ていないものもあり?
続いてカルパッチョ風お刺身 Oさん作
第2陣到着の方も入って皆でパシャ!
今年は途中、友人Hさんのパパが、尺八を演奏。
テーブルの人口密度が下がってもう1枚!
Hさんと友人のAさん
やっぱり8時間も飲んでいるせいでしょうか、酔いが...
この時間帯は第3陣のゲストが合流、結構お酒も入っていて皆リラックスモード
桜の花はまだ一足早く一部咲きにも満たない感じでしたが、皆さんそれぞれにパーティを楽しんで頂けたでしょうか。
by bandoh
イベント、観劇 : 16:55 : comments (x) : trackback (x)
2009-03-25 Wed
3月24日WBC決勝戦 サムライ日本優勝おめでとう!!!!!!
何だか、とっても嬉しい!
夜の水天宮近辺では、酔っ払いがあちらこちらで出没していて、帰り道に「祝杯」でも、あげていたのではないだろうか?と想像してしまいました。
帰り道、水天宮駅から電車に乗ってホームを見ると、酔ってヘロヘロになったサラリーマン二人がいましたが、
目があったかと思ったら、なぜか二人とも、笑いながら電車の窓のすぐ近くまで走りよってきて、私と連れの2人に向かって、思いっきり顔を窓に近づけて両手を振っています。(やだやだ)
私達3人とも最初ちょっと怖かったんですが、その顔があまりにも緩んで間抜けで"Happy"そうなので、おかしくて、こちらも振り返してあげました。
今宵はみな、Happyなのかしら...
さて、話しを戻すと、"イチローファン
イチローがしぶとくファウルを打ち続け、勝越し打を決めたき、思わずガッツポーズ
多分、あの瞬間、日本列島のあちこちで、興奮のどよめきが一斉に起ったと思う。
スミマセン、以下イチローの写真ばっかりです。
バンザ~イ ニッポン!
振返れば、決勝戦1回表 イチローの初打席
来た~!! ヒットの予感!!
ヒットだ~!! 幸先がいいわ~
走るイチロー
真剣...
そして、10回表 勝敗を分ける運命の打席
またもや、きた~!! 神が降りてきた~
場内がどよめき、嬉しそうに"日の丸"もたなびく
やった~! 3対5!!
WBCがスタートして、イチローは苦しんでいた。
納得のいくプレーがなかなかできず、谷ばかりで山がないと感じていた。
だからこそ、決勝戦の最終回の「勝越し打」は、彼にとって大きなギフトだったと思う。
あの局面で、きちんと期待に沿えるのは、本当に限られたプレーヤーしかいない。
そういう意味で、やっぱりイチローはすごいと思う。
「ここで打ったら、その後、盛り上がるだろうなぁ~」とインタビューで答えていたので、ものすごく内的会話があったらしい。
イチローとの勝負に挑んだ、韓国チームの監督に感謝である。
(これ後で分かったのですが監督は見送りのサインを出していたようですね)
どんなに、天才的なプレーヤーでも、十割なんて決して打てないのが野球である。
プロは、並外れた才能とセンス、たゆまぬ努力、メンタルタフネス、そしてその時の調子の全てが求められる。
イチローがメジャーリーグにデビューした年、彼のプレーを見ていて鳥肌が立った。
NOMOが既にメジャーでは活躍していたが、野手で活躍していた日本人プレーヤーは当時まだいなかった。
どんな球にも合わせられる絶妙のバット・コントロール、俊足を生かした盗塁、ライトからサードへの弾丸のような"レーザービーム"と呼ばれる送球。
きっと10年に一人出るか出ないかの選手だろう。イチローは、ゲームを動かす小気味の良いその新鮮なプレーで、アメリカのベースボールファン達を熱狂させた。
そして、もう一つ、私は今回の「日本チーム」の一丸となった姿と、チームプレーに感動した。
野球はチームプレーであると、つくづく感じてしまった。
それをまとめた原監督も偉い。
例えば米国チームは、選手の体も大きく、ガンガンホームランを打つような4番バッター、強打者揃いである。
でも、1人1人が能力の高いバッターだとしても、一つのチームとして、お互いに有機的に結びついた「戦略」と「プレー」と「皆で勝つ思い」がなければ、勝てないのである。
個人パワー中心の本塁打に頼っていては、チームプレイ(走塁を進める)の野球に対して打ち勝てないのである。
これらは、米国チームの大きな弱点であると思う。
おそらく、米国は今回の敗退の原因として、表面的な「戦略」や「技術」を分析するかもしれないが、その根底にある"人の自発的なチームへの貢献意識"については、掘り下げないだろうと予測する。
イチローは、メジャーリーグで長年プレーし、多種多様の人間が主張しあう「混沌」とした個人主義の社会で揉まれているので、芯からそれを知っていると思う。
またメジャーに行ったことによって、自分の夢をかなえ、そしてどこかの時点でチームのあり方に失望し、外から日本のチームプレーの良さを「再認識」したのではないかと思う。
そして、彼の中に眠っていた"日本人"も目覚めたと思う。
この話し、会社経営にも、応用して考えることができると感じました。
90年代にバブルが弾けて以来、企業は米国型マネジメントを取り入れ、「改革」のもと、早期退職も含め、多くの人材をリストラし解雇した。
そして、その後に「成果主義」を導入したことによって、日本の会社にあった、チームで互いに助け合うといった文化が薄らぎつつある。
私達はバブルの反省から、この十数年で、合理的なマネジメントを信奉し、それに慣らされてしまってきているが、今一度、原点に戻り、日本的経営の良さを見直し、新たな道を開く必要があるのではないかと思う。戦後復興してきた真のパワーが何であるかを見直す必要があると思う。
「成果主義」は、本当に人のモチベーションを高めているのであろうか?
「報酬」にモチベーションを求めることで、人は本当に伸びるものなのか?
「雇用の不安」は働く意欲そのものを下げているのではないだろうか?
経営が「合理」に走りすぎて失っているものはないだろうか?
日本人は、強者弱者を含め、一人一人のポテンシャルを有機的に結び付け、組織のパワーとして生かすことが、どこの国の人よりも上手いのである。
一人一人のちょっとした気配りと配慮と努力が積みあがると、大きな成果を成すのである。
企業は、もっと小さな村社会的チームワークの良さを、再認識すべきだと感じてしまう。
価値を再確認しよう!

by bandoh
徒然なるままに : 02:31 : comments (x) : trackback (x)
2009-03-23 Mon
先週、姉との会話でグラミン銀行のユヌスさんの話題が出た。
姉はこのブログを読んでくれているので、先日の「ユヌスさんの講演」の話しを読んで、女性支援の活動に関心を持ったらしい。
PTAや地域の子供の教育支援等の活動にずっと従事してきているので、そのネットワークの中で出会うシングル・マザーの苦労を知っているのだと思う。
生活環境や性格や行動パターンが違う姉と、共通の関心ごとを持つのは、実はそんなに多くはない。
例えば、私は学生時代は"スポーツ"を中心にクラブ活動を行っていたが、姉は"音楽"が中心だった。
そして、私は子供を持たず働いていて、おまけに会社を飛び出し独立してしまったが、姉は子供が二人いて専業主婦、組織にきっちり忠誠を尽くすタイプ。
私は新しいオーディオのセットが自宅に届いたら、バリバリ箱を開けて"取扱い説明書"も読まずにボタンをドンドン押してやり方を憶えるけれど、姉はまずじっくり"取り扱い説明書"を読んでから、ゆっくり機材に触る。
姉はエスニックフードのような香辛料の強い料理は苦手だが、私は好き。
私は思いついたらすぐ実行、姉は石橋を叩いて叩いてわたるタイプ。
私は寒がりで姉は暑がり。
こうやって客観的に見れば違う面に気づくことが多い。
でも子供の頃を思い出すと、姉とはいつも一緒で同じことをしていたような気がする。
母や姉の話しによれば、まだ幼稚園にも上がらない私は、どこへ行くにも金魚のフンのように姉にくっついて歩いていたそうだ。
私より4歳年上の姉は、近所の同級生と遊ぶのに、私を連れて行かなければならないのが本当に嫌だったそうだ。
でも、私を連れて行かないと母から怒られるので、仕方なく毎回連れて行ったらしい。
私が行くと友達のジュンちゃんから「ユウちゃん、またフミちゃん連れてきた~
私の記憶に残っていることで、その当時を裏付ける出来事がある。
いつものごとく、姉と姉の友人たちと近所の公園で遊んだ時のことだと思う。
気がつくと、思いのほかとっぷりと陽が暮れてきていて、あわてて皆がそれぞれの自転車にまたがり、家路に向けて出発したときのことだ。
姉は必死に「ジュンちゃ~ん、待ってぇ~、みんな待ってぇ~」と前を行く友達に向けて叫ぶが、皆ドンドン先へと行ってしまう。
家に早く戻らないとすっかり暗くなってしまうので、皆必死に自転車を漕いでいて、おそらく風下の姉の声は聞こえないのだろう。
姉はと言えば、その中でただ1人妹を自転車の後ろに乗せているため、重くて友人たちのように早く走れないのだ。
漕げども漕げども、距離は広がるばかり。そのうちに皆の姿は遠くなり見えなくなった。
姉の苛立ちとくやしさは、そのとき頂点に達したのだろう。
「フミちゃんがいるから、フミちゃんのせいでこんなことになるんだよ~、みんな先に行っちゃったじゃないのよ~
あの時、私も幼いながらも、姉の"皆と一緒にスイスイ帰りたい、でも妹を置いては帰れない。"アンビバレントな気持ちがよ~く分かった。
「お姉ちゃん、大変なことになっている....。
思えば、責任感の強い姉の性格は、こうやって形成されていったのではないだろうか。
そして、私は中学校に入るまで姉の影響を強く受けることになる。
思えば私はいつも、よく動きせっかちな母の膝の上ではなく、ゆったりと動かない姉の膝の上に座っていた。
姉が見たいTV番組を私も好きになった。「ウルトラQ]、「ガッチャマン」、「題名のない音楽会」、「兼高薫世界の旅」などよく憶えている。
兼高さんの番組が始まると、今はなきパンナムの映像が映りテーマ・ソングが「ラ~ リ~ラ ル~ラ リ~ララ~
懐かしいですねぇ。下は70年代にカブールへ行った兼高さんです。
あの楚々として優雅な語り口と、堂々とした態度や行動、かなりインパクトがありました。
"国際人とはこうだ"と脳裏に植えつけられたように思います。
私が「旅好き」になったのは、この番組の影響が大きいと絶対に思う。
そして「本」も、姉からの影響を受けていた。
姉の本棚にある世界の名作文学集や、「赤毛のアン」全シリーズや小説、海外ノベルなんでも読んでいた。
イチ早く「荒井由美」のアルバム「ひこうき雲」を買ってきて、「これ、最近出た人なんだけど音楽が新しくていいよ。」と教えてくれたのも姉である。
お陰で、私は今でも友人と共に松任谷由美のコンサートに行く。
また「ロードショー」好きの姉の影響で、私も「映画好き」になってしまった。
姉が中学生、私が小学生の頃、一緒に「メリーポピンズ」を観に、二人で有楽町まで出かけた。
確かあのときは、2階の指定席に座ったと思うが、何だか姉にくっついて、すっかり大人になったような気持ちになったものだ。
真面目でいつも優等生で、周りの大人たちからよく褒められていた姉。
とにかく私の中の姉は、いつも「頭が良くて何でも知っている、すごい大人」だった。
さて、大人になるにつれ、私の中に"眠っていたDNA"のスイッチがONとなったのかどうか知らないが、クラブ活動や学校の同級生達の影響を受け始めると、私と姉との間に「違い」が出てくるようになった。
そして、姉が結婚した後は、互いの「生活環境」が変わってしまったこともあり、だんだんとコミュニケーションが少なくなっていった。
しかしながら、4年前の父の病気と死を境にして、再び姉とのコミュニケーションが増えるようになった。
家は両親共に愛情深く、父は子煩悩な人で、よくピクニックや海水浴、温泉、紅葉など家族旅行に連れて行ってくれた。毎年お正月に泊まっていた温泉旅館の混浴(すごい)のお風呂が、広くて楽しかったことを今でもよく憶えている。そういった意味では私たち姉妹は恵まれた家庭環境で育ったといえるだろう。父には感謝である。
姉とのコミュニケーションが増えるようになったのは、父の病状を案ずることや、亡くなった悲しみを共有することを通して、自分達が「家族」であることを、再意識させられたからに他ならない。
「私には私の世界があるが、姉には姉の世界がある。」
そのお互いの世界について、私達は情報を共有するようになってきた。
姉妹でもお互いに違っていて当たり前。
大事なことは、「何が違うのかを理解する」ことなのであろう。
姉が、私にユヌスさんの話しをして、同じように関心を持っていることを知ったとき、学生時代の頃の記憶が甦った。
「正義感」が誰よりも強く、公正ではないと思うことには、涙ぐみながらに抵抗し、年長の男性にさえ、くってかかる姉の姿である。
一見すると私の方が過激に映るだろうが、実は姉の方がずっとエネルギッシュで内に思いを秘めた人なのである。
「三つ子の魂百まで」というが、ユヌスさんの話しによって、子供の頃に互いの間で繋がっていた「価値観」が何か反応したような感じもした。
姉のボランティア活動も、今後どのように進展していくのか興味深い。
by bandoh
コーチング : 09:00 : comments (x) : trackback (x)
2009-03-19 Thu
自宅の近くには、斜面に沿ってうっそうとした「竹林」がありました。
歩いている途中、いつもその竹林の所に出ると、奥には何か野生の獣(たぬきなど?
この地域の家は、どこも庭に「花」や「木」を植えて(猫の額のようなどんな小さな庭であっても植えています)、季節にそってそれぞれの表情を創り、近所の人を楽しませてくれています。
その家の一軒に、私が「秘密の花園」と名づけた家があります。
その家は、日本では珍しい、淡いグレーに近いペールブルーのペンキに塗られた洋風で清楚な感じのお宅です。
そして広い庭には、絡まって伸びるツタなど、無造作で野生化したように見える、花々や木々が植わっています。
家同様に洋風で無造作なその庭は、うっそうとしていて微妙に侘びさびのある枯れた風情をかもし出しています。
そして、目を凝らしてみると、その奥にひっそりと、やはり同じペールブルーのガーデンテーブルと椅子が置かれています。
その家がミステリアスなのは、いつもシーンとしていて、窓はぴたっと閉じられカーテンが下がり、人が住んでいる気配がないことです。
しかし、その庭の花がわずかに手入れされている痕跡を見ると、人が住んでいるとしか思えません。
毎回この家の前を通るたびに、ある日、国籍不明な感じの白髪のおばあさんが、花バサミを手に出てくることを期待しつつ、竹林同様、ジっと見入ってしまいます。
こういった庭や竹林、そして畑(生産緑地)は、家の近所の「のどかさ」を醸し出す大事なパーツに思えます。
(ちなみにWikipediaに写されている生産緑地の写真は家のご近所です)
これは収穫の時期になるとやってくる小学生
「農業体験」なんでしょうが、大根とかお芋とか掘って帰るようです。
でっかい大根ですよねぇ~。大蔵大根という種類のようです。
ちなみに、ここの畑は、自宅の隣なのですが、畑横のテーブルの上に毎日収穫物が並んでいます。("世田谷育ち"と言うブランドです)
無人なので、置いてある箱に100円を入れて作物を持って帰れます。
先生も指導大変ですよねぇ。もしかしたら畑のお兄さんかもしれません。
女の子が重そうなスコップを持って、掘っています。
頑張った後は、皆でお弁当を広げて食べています。
この時期に入ると、「秘密の花園」や近所ではミモザが咲き始めて、綺麗な黄色が心を浮き立たせてくれます。
さて、その近所に、最近大変残念なことが起こりました。
今年に入ってからですが、その大事なパーツである竹林がすっかり伐採されて、変わりに斜面がむき出しになってしまったのです。
小田急電鉄が所有する土地となった(元々所有していたのかもしれません)ようなのですが、宅地のための「造成工事」が始まったからです。
フェンスが張られ、トラックやシャベルカーが入ったかと思ったら、しばらく経って、あの「日本昔話」に出てくるような竹林は、姿を消してしまいました。
まぁ、人が住む以上、仕方のないことだと思いますが、本当に心から残念です。
自分だってそうやって造成された土地の上に住んでいるわけですし...。
こうやって、いつも近くにあると当たり前だと思っているのでその価値に気づかないのですが、無くなってしまってから「あぁ~」気づくことってありますよね。
これは、近くの木を撮影した写真です。
ドンドン開発されて、寝ぐらや捕獲などのテリトリーを失っている鳥達は、わずかに残されている木に密集しています。
ピーピー、ギャーギャー聞こえてくる鳥の鳴き声が、最近のエサ不足を嘆いて怒っているようにも聞こえます。
何だか、こうやってみると木に「鳥の実」がなっているようですよね。
家の隣の畑が、開発される話しを聞いたら「引越し」かなぁ~
by bandoh
徒然なるままに : 15:18 : comments (x) : trackback (x)
2009-03-17 Tue
日曜日に、ノーベル平和賞受賞者の「ムハマド・ユヌス氏」のセミナーに参加しました。
タイトルは「貧困のない世界を創る~ソーシャル・ビジネスと新しい資本主義」です。
以前、ハリウッド女優の「ナタリー・ボートマン」が特集された番組を見たときに、彼女が「マイクロ・ファイナンス」を通して、貧困層の女性の支援をしていることを知り、そこで初めて「マイクロ・ファイナンス」という言葉を聞きました。
マイクロファイナンスは、どちらかといえば、ハリウッドのスターが、自らのイメージを高めるための救済活動としては地味で、華々しくマスコミで取り上げられることが少ないのだが(アンジェリーナ・ジョリーがアフリカの子供達を抱いている写真みたいな"絵"になるものもないですからねぇ)、確実に支援を受けた女性が自立していける手法として印象が残った記憶がありました。(ナタリー・ボートマンの知的なイメージと噛合っています)
ユヌスさんは、その「マイクロ・ファイナンス」を創った人なので、今回はかなり高い期待を抱いてこの記念セミナーに参加しました。
ムハマド・ユヌスさんの講演は、予想以上に意義のあるものでした。
天気の良い日曜日の午後に、外で遊ばずに来た甲斐がありました。
すっかり、ムハメド・ユヌス氏のファンになってしまいました。
彼が始めた「マイクロ・ファイナンス」や、その後に続く「ソーシャル・ビジネス」の「社会的意義」や「独創性」もありますが、信念を持って幾多の困難を乗り越えたその「姿勢」と「哲学」、「先見性」には驚かされます。
まず「マイクロ・ファイナンス/クレジット」を初めて聞いた方のために、少し注釈すると。
グラミン銀行が始めた「貧困層」を対象に行った小額のローンです。
20ドルとか40ドルを借りて、1年間で返すことが基本です。
ローンを行っているグラミン銀行(ユヌス氏が創設)は、通常の銀行とはルールと仕組みがまったく違います。
・まず、通常の銀行では貧困層の特に女性にはお金を貸しませんが、グラミン銀行では貸しています。
・また通常の銀行が行っている審査(過去を問うこと)をしません。過去に不履行や犯罪などの経歴があっても貸します。過去ではなくその人が何をしたいかを問います。
・借り手に担保などは要求しません。(ないですから)
・また、グラミン銀行は、経済状況などの変化で、途中で「借り手」が苦しくなり、「返済が滞るような状況」が起きた場合には、返済額を変える、償還期日を延期するなど、「柔軟に対応」します。
グラミン銀行の基本的な理念は、「貧困層にある困っている人たちを支援すること」です。
そして「人々の自立を促していくこと」です。
ユヌスさんは、「我々は貧困で苦しんでいる人たちに、更に鞭打つようなことはしない。」と言っています。
ビジネスですから、利益を生み出さないと継続していきませんので、勿論銀行は利益を出しますが、配当については利益をつけません。
元本はお返しするが、無利子/利益です。しかし、もちろんグラミン銀行の預金者には利益は付加されます。預金については年間10%の利子がつきます。(私たちも東京から"預金したい"ですよねぇ。)
このマイクロファイナンス/クレジットにより、「字も読めず、一生奴隷のように生きていくしかなかった貧しいシングルマザー」が、小額のローンによって商売を何とか始め、自立し生きていく道を切り開いていきます。そして、自分の子供に教育を受けさせるお金を、グラミン銀行から借りて子供達に高等教育(大学まで)を受けさせることができるようになっていきます。貧困からの脱却です。
また、グラミン銀行のデフォルト率(債務不履行)は約0.5%だそうです。
厳しい審査を経て貸付を行っている日本の銀行の債務不履行が1%以上あることを考えると、貧困層を対象にしたグラミン銀行の0.5%は凄いことだと思います。
ユヌスさんは米国の大学への留学後、国(バングラデシュ)に戻り、貧困にあえぐ人たちをなんとかしたいと思っていました。
しかし経済学の博士号を納めた彼は知識は持っていましたが、すぐに優れた理論があっても何の役に立たないことに気づきます。
目の前で飢餓によってドンドン死んでいく人を見ながら、その人たちを救うためにどんなことをしたらよいか全く分からなかったそうです。
そして、教科書を捨てて、学んだことの全てを忘れようとしました。
そして、彼は大学の隣にある村に足を運び、そこの住民の話しを聞き実際何が起きているのかを知ろうとしました。
実際に見聞きして調べるうちに、驚くべきことにあたります。
「高利貸し」から、お金を借りている貧困に苦しんでいる人たちのことです。
生活のためにわずかな金額を借りて、1週間で10%もしくは1日10%というような高い金利を払っている人たちです。
そのために、生活を縛られ、ほんのわずかなお金で生きていかなくてはならなくなっていました。
一生懸命働いても働いても、システム上借金がかさみ、その苦しみから解放されるのは死しかないという悲惨な状況です。
調査を進めると、そうやって「高利貸し」からお金を借りて苦しんでいる人たちが、村には「42名」いたそうです。そして、なんとその42名の「借金の総額」は、たったの「27ドル」だったそうです。
ユヌスさんは、たった27ドルの利子を払えずに、一生搾取され、奴隷のように働かされる人々の境遇にとても胸を痛めました。
そこで、ユヌスさんは「解決策」を考えます。
彼らの代わりに、彼がその27ドルを払ってあげることに。
そして村人達は自由になり、ユヌスさんは大変村人達から感謝されました。
「だったら、もっと出来ることがあるんじゃないか?」とユヌスさんは考え始めます。
それが、貧困層の人たちへのローンを始めるきっかとなりました。
そして、そこに行き着くためには、長い長い道のりがあります。
ユヌスさんは言います。
「私は銀行のことなんて、何も知らないから、枠にとらわれずに考えることができた。」
「既存の銀行を調べて、全てその逆のことをやってみた。」
「ビジネスにおいて人は、"人間というものを狭く定義している"。人間というものはもっと広くて独創的だ。利益を追求する人もいれば、社会のためにもっと貢献したいと思っている人だって沢山いる。」
「人は皆、"可能性を秘めている。"その潜在的な能力を引き出せば、誰でも必ず自立し成功できる。そして自らのビジネスをスタートできる。」
「今の会社は、利益の追及が目的となっている。本来は利益はその結果でしかないはずだ。責任ある利益の拡大化が必要だ。」
「政府にだけ頼っていても駄目だ。政府はやりたいことをやればいい。政府は本来構造的に早く動けない、また捨てられないものが沢山ある。だけど人は自由ですぐに動けるし、止めようと思えばすぐに止められる。だから問題は我々自身が解決できる、自分自身についてあきらめてはいけない。全ての個人は"企業家"なのです。」
おそらく、彼の理念と信念に触発を受け、社会に役立つ、"ソーシャル・ビジネス"を始める日本人の若い人たちが、これからはもっと増えてくるのではないかと思います。
セミナー会場にも、すでにソーシャルビジネスを始めようとしている20代の女性や、バングラデシュでグラミンのやり方やソーシャル・ビジネスを視察し学んできた20代の若者がいました。
私自身は、今回のムハメド・ユヌスさんから、「人には必ず可能性がある。その力を持っている」と信じるパワーを貰いました。
コーチングにぜひ、生かしていきたいです。
by bandoh
コーチング : 09:00 : comments (x) : trackback (x)
レストラン、ショップ : 12:39 : comments (x) : trackback (x)
2009-03-12 Thu
久しぶりに甥のケンタと電話で話す。
就職活動が最悪の状況とのこと。
先日、主人から「戦後最悪の新卒採用状況らしいよ」という話しを聞いた。
ケンタも、色々と企業に出向き、面接を受けているがなかなか良い返事を貰えないらしい。
ノンビリ屋の甥も、これではまずいと思っているらしく、来週は「四国」にまで会社説明会に出向くとのこと。
「なんで、そんな遠いところに行くの?」と聞くと、
「う~ん、四国まで行けば、あいつら来ないと思うんだよねぇ。」とケンタ。
「あいつらって誰?」
「慶応とか早稲田の奴らのことだよ。会社説明会に来ているポン大とかその辺の学生とお茶飲みながら、話したんだけどさ~、普通、早稲田の学生が、武蔵野の"N協"まで面接に来るかって。通常だったら来ないよねぇ~。だから、あいつらのいないところに行きたい。」
「ふ~ん、なるほどね~。こういう時期だから競争は厳しいよね。でも今努力していることは、何であれ必ずプラスなことに繋がるから、頑張って続けてね。それと、面接に残ったら、出身校よりも個人を見られることになるから、その点をしっかり忘れないようにね。きちんと大学の就職課の職員以外の人からも、面接についてのフィードバックを貰った方がいいよ。」
と伝えて、電話を切った。
自分が行きたい領域の、"強敵の少ない戦地"に赴き、勝利を得ようという戦略らしい。
しかしながら、具体的にどう勝ち残るかの「戦術」については、見えている決定打がないようだ。
まだまだ、自分自身についての"見かた"が浅いと感じる。
以前、「就職氷河期」に就職活動をしたことのある女性から聞いた話しだが、採用の通知がなかなか来ず、沢山の企業を本当に沢山訪問したらしい。
頭の良いしっかりした女性なので、これまでの人生において、数多くの"NO"を突きつけられる経験など、あまりしてきていないだろうと思う。
他人からの否定は何であれ自信を失うことに繋がる。優秀ゆえに、その時期はさぞ辛かったことだろう。
彼女は、日々自分の弱気に負けないよう、面接の途中、カフェに立ち寄り、自分を励ますために日記をつけていたらしい。
そして、その日記を見ると、「これを乗り越えたんだから、私には出来るはずだ」と、悩みを持っているときにも思えるそうだ。
人生って、自分自身の過去から学べることが、実は沢山あるもの。
"人生の難関を突破した経験"なんて、まさにそうだと思う。
「採用が決まる」ことは大事だけれど、
ケンタがこの難関をどう乗り切るか、これも人生においては価値があると思う。
就職浪人となると、復活戦がかなり大変らしいが、人間、逆境に陥ればその分、強くなる可能性も高い。
私自身は、甥には色々な難関を今後乗り越えていくバイタリティがあると感じる。
さて、今後の甥の人生の舵取り、一体、どうなっていくのか....。
by bandoh
徒然なるままに : 14:35 : comments (x) : trackback (x)