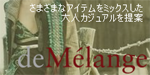| << NEXT | Main | BACK >> |
2010-05-12 Wed
GWに久しぶりに会った知合いから「物理脳」と「化学脳」の話しを聴いた。
「物理脳」というのは、
仮説を設定し検証していくメカニズムの強い脳のことを指す。
演繹法と帰納法とで言えば、演繹法の考え方となる。
一般原理から推測論理的推論により結論として個々の事象を導く思考となる。
一方「化学脳」は、
帰納法の考え方の強い脳となる。
とにかく実験、実験(やってみて)で傾向をつかんでいくやり方である。
演繹法とは逆に、個々の事象から事象間の本質的な結合関係(因果関係)を推論し、一般原理を導く思考となる。
私自身、「物理脳」と「化学脳」のどちらが強いかといえば、おそらく「化学脳」だろうと思う。
自分のビジョンを描き、具体的な道筋を導きだすくときにはとりあえず「物理脳」を使うが、日々の行動は、わりと思いつきとかひらめきでパっと行動を決めることが多い。原則原則に従ってというよりは、いい加減でゆるい部分が沢山ある。
元々勤めていた不動産会社で、企画部門にいて沢山の高層住宅の事業計画の結果を見てきた影響も大きいかもしれない。
当時の企画部門では、年間1500億円程度の首都圏を中心とした高層住宅の事業計画の目標があり、その目標は企画本部内の各部に割り当てられる。
毎週、事業化に向けて各部の担当者から企画物件が上程されるのだが、販売が上手く行くという根拠については、周辺の相場や立地、環境など、さらに「マンション売れ行き情報」などのデータをもとに、成功するという根拠をもとに仮説が立てられて事業計画書が作成される。
そして、役員会議を経て企画物件は、事業決定されるのだが、必ずしも販売が成功するとは限らない。
正しい根拠をもとにした仮説があったとしても、予定通り物件は売れないのである。
企画物件は、企画から1年以上を経過して販売されるので、その間に予測できなかった景気などの市場環境の変化を受けるということが一つの理由となる。
さらには、担当者自身の問題がある。
企画が成功する仮説を立てようと思えば、用いるデータは自分に都合の良いものを選び上手く加工し、不動産のプロではない役員さんの目をごまかすことができる。
年間の企画目標を割り当てたられた担当者は、プレッシャーからとにかく企画をあげて事業化し目標を達成せねばという心境に陥るので、企画に弱点が若干見えているとしても、販売するのは他部門なので「えいや!」という気持ちになりやすい。
上場していて余剰資金の少ないデベロッパーほど、売って仕入れて、売って仕入れての繰り返しで利益を稼ぐ必要があるので、自転車操業となり、「えいや!」組が増えてしまう傾向にあると思う。
このケースでの「えいや!」は、「もしかしたら、なんとなくまずいかなぁ~」という感じを持っているけれど、その感覚を無視して突っ走るときのえいや!である。
えいや!は、“組織の財布でものを決める時”、“思い入れや我欲に走ったとき”、“自信過剰の時”、“ねばならない状態”にはまった時に出やすい一面である。
そんなえいや!の「仮説」も見てきたせいか、論理でバリバリに固められた仮説ほど、胡散臭さがつきまとう。
ところで特にこの数年企業では、これまで以上に業務のプロセスやコミュニケーションなど、様々な分野で早急な課題解決が求められている。
カスタマーニーズの変化、IT技術の発達と情報化社会の進化など市場環境の変化はめまぐるしく、まったなしの変化に対応するスピードが求められているからである。
その影響もあり、企業ではリーダー層に「論理的思考法-ロジカルシンキング」という分野の教育を取り入れているところが多い。
しかし、この思考法、さきほどの「えいや!」ではないけれど、気をつけなければ、間違った方向に人を導くことがあるし、まったく機能しないことがある。
例えば、かつての会社で企画を担当していた管理職のIさんは、周りの人が口論で勝てない独自の論理展開があり、その論理武装に誰も打ち勝てないというアグレッシブな男性であった。しかし私が入社する前の彼の企画物件の成果はどうだったかよく分からないが、彼が進めていた事業は、その後社内を知る人の話しによれば全て失敗もしくは赤字となったらしい。怖い話しである。
また、某会社で進められた改革案は、理にかなったすばらしいプロジェクトであったけれど、猛烈な現場の抵抗によって進まず、担当役員さんは責任を感じて辞職することになったことがある。
そんなミスリードだったり抵抗を減らしてくためには、左脳だけではなく、やはり、右脳(感性)も活用して、問題解決を図ることが大事であると思う。
さらに、民主党のマニフェストではないが、途中経過をきちんとニュートラルに検証して、必要な修正を加えていく柔軟性が必要であると思う。
しかし、右脳(感性)も活用した問題解決は、一体どのように行うと良いのか?
問題解決のツールとして1つお奨めするならば、私自身は、NM法をお奨めしたいし、その後の柔軟性も加味するならばSFAの活用もお奨めしたい。
NM法は亡くなられた中山正和さんが開発された問題解決の発想法である。
イメージや形容詞(感覚的な言語)を使うことによって、右脳を活用して解決にいたる発想を創造的に行う手法となる。
NM法が秀逸なのは、どんなに感性が鈍い人でも、必ず創造的な発想を導きだせる点である。
ご興味ある方は、アマゾンで中山さんの「発想法の書籍」が買えます。
さらに、柔軟に修正を加えていく考え方としては、S.F.A.(ソリューション・フォーカス・アプローチ)がシンプルで簡単である。
問題解決に向けて、出来ることを1歩づつ積み上げて、確実に進んでいくやり方で、かなり柔軟な対応が取れる。
また、具体的に出来ることを1歩づつ進めていくので、誰でも実行できる。
さらにこの手法は、上手く行っていないことの原因分析を一切しないので、その分解決策を導く時間を削減できるし、組織で働く人のエネルギーが下がらない。
いま、アメリカやヨーロッパの会社組織では、SFAやAIといった「ポジティブアプローチ」による問題解決が主流の一つともなっている。
そのほうが、問題解決が早くて効率的という結果が出ているからである。
「ポジティブ・アプローチ」は、もともと、心理学から派生して出来た手法なので、
人間の“心理や感情”を踏まえたうえで考えられた組織の「問題解決」や「組織開発」の手法となっています。
その心理学の背景を言えば、現在の問題を過去の幼少期のトラウマウにさかのぼって、何十時間かけてていくら検証してみても、現代の問題の完全解決にはならないと臨床から悟ったセラピストや研究者たちが、「フロイトよさらば」とばかりに生みだした“N.L.P”や“ブリーフ・セラピー”であり、今のSFAやAIなどのアプローチに大きな影響を与えています。
結局、どんなに正しいと思える解決法も、人がやる気になって取り組まないと、上手くいかないし、社会は複数の人がいる限り常に変化するので、今正しいと思える解決策も変わる可能性があるという過去の経験から、必然的に生まれてきているのだと思います。
この、60年代、70年代のアメリカ西海岸を中心とした様々なセラピーやワークショップの取り組みは、今振り返ってみれば、大きなイノベーションだったのだと思います。
何だか、ダラダラと書いてしまって、
結局、知合いから言われた「物理脳」と「化学脳」によって、「ポジティブ・アプローチ」がやっぱり問題解決や組織開発には成功率が高いということに帰結してしまった。やっぱり私は、「化学脳」
by bandoh
徒然なるままに : 16:38 : comments (x) : trackback (x)
2010-04-08 Thu
伊勢について3日目の朝、ラウンジで朝食をとる。
本日も天気が良い。
F女は目ざとく母のターコイズのブレスを見つけ、
「お母さん、素敵ですね!」と褒めてくれる。
F女はぜひ"鳥羽国際ホテル"に立ち寄ってから、鳥羽を出たほうがいいと言う。
昨晩鳥羽の町で食事をした他の3人は、食事後、Y女史の案内で、眺望が素晴らしいという彼女のお気に入りのホテルに行ったそうだ。
ただし残念なことに、日もトップリと暮れた後だったので、肝心の眺望は見えなかったらしい。
「鳥羽国際ホテル」に到着してみると、お奨めした理由がよく分かりました。
立地が良いため、本当に眺望が素晴らしい!
みな、身を乗り出して左側サイドの鳥羽の海の景色に見入っている。
右側サイドをみれば、鳥羽の港と町も見えます。
つまり、ラウンジの広がった窓から、広がる鳥羽の海と町の両方が見える。
表のデッキに出てみると、更に景色がうーんと広がって見える。
天気もよくて暖かく、ここでコーヒーを飲んでしばらく鳥羽の景色を堪能。
次回来るときには、この鳥羽国際ホテルのオーシャンウィングに泊まるのもいいなぁ...。
鳥羽10:36発の近鉄特急に乗って奈良へ。
ただし、途中「大和西大寺」の駅で、乗り換える必要があるのですが、
チケットを見ると乗り換え時間が1分しかない...。
車掌さんに確認すると、乗り換えの電車はホームが違うので、
階段を上って高架の橋を渡らなくてはならない。
とりあえず、私が自分と母のスーツケースを持ちダッシュ。
その後に母がついてくる。
そういえば、2年前のローマのテルミニ駅で、フィレンツェ行きの特急に乗るのに、同じようにして母と走ったことがある。
あの時も間に合ったが、今回も何とか間に合った。
やれやれ....
しかし、奈良までいく電車に乗っていて
とても興味深いのは、近鉄線が「平城宮跡」の中を横切っていることである。
高架もかけられないし、地下も掘れないだろうから致し方ないのだろう。
クリックして図を開いてもらえば、どう横切っているかが分かる。
電車に乗って窓の外をみると、
遷都1300年で復元された「第一次大極殿正殿」などが見えてくる。
奈良駅では、MKの運転手さんが出迎えてくれていた。
森村展夫さんという上品なおじいさんである。
実は森村さんに観光をお願いするのは、京都も入れると今回で3回目となる。
さて、その森村さんの案内で、まずは「唐招提寺」へ
唐招提寺は南都六宗の一つである「律宗」の総本山です。
幾たびかの苦しい航海を経て、
日本に仏教者に戒律を授ける「導師」として招聘された鑑真大和上は、
759年に戒律を学ぶ人たちのための修行の道場を開きました。
それが「唐招提寺」の始まりで、当時は「唐律招提」と名づけられ鑑真和上の私寺でした。
当時はきちんと「戒律」が整備されていなかったので、
勝手に出家得度する人とか、グチャグチャして困ったことになっていたのでしょう。
5回目の渡航で弟子に死なれ、自らは失明してしまい、
6回目の渡航でようやく日本に辿り着けたとき、鑑真和上は既に66歳。
ものすごく深い信仰心と意志の強さがなければ、できないことだなぁ...と感じいる。
手前:金堂、左:講堂 右:鼓楼(仏舎利が納められている)
ちなみに、中国の主席などの要人は、来日すると必ず唐招提寺に来られるそうです。
共産主義ゆえに拝んだりはしないのかもしれないが。
「金堂」の前で母と記念撮影
金堂には、本尊の「乾漆の盧舎那仏(るしゃなぶつ)」、「薬師如来」、「先手観音」などがある。
「先手観音」はかなりインパクトがあり、目を奪われてしまう。
この日の奈良は、初夏のようにお天気がよく暖かく、桜がまた綺麗...
そして、次は「薬師寺」へ
薬師寺は法相宗のお寺で、檀家を持たないお寺である。
(お参りする人には行事への参加や自宅での、「写経をお奨め」していますが、写経による寄進によって建物が復興されています)
ここは、薬師寺に入る手前にある「薬師寺休丘八幡宮」である」
明治維新で、廃仏毀釈が行われるまで日本の神社とお寺は一体だった。
という訳で、薬師寺にも鎮守として神社があるとのこと。
ちょっと「へぇ~」って感じなお話しであるが、
もともと、神社とお寺が一体だったというのは、両宗教間の対立を避けたのか、わりと左脳的説明というか説法のある仏教が広まったことで、天皇が神社の位置付けを明確にしたかったのか、何かあったのかもしれませんね。
実は、明治の廃仏毀釈以降で寺院が神社を管理するという形態が残っているというのは非常に数が少ないそうだ。
薬師寺別当の栄紹法師が僧形八幡神、神功皇后、仲津姫命を勧請したのが始まりのようである。
さていよいよ「薬師寺」の伽藍へ
写真は薬師寺の「東塔」(とうとう)(国宝)である。
薬師寺は飛鳥にあり、710年平城遷都で現在の地に移ってきたといわれている。
建立当時は、「龍宮造り」と称えられるほど華麗な伽藍を誇っていたそうだが、
度重なる消失で当時から現存しているのは、上記の写真の「東塔」だけである。
玄奘塔は始祖・玄奘三蔵(西遊記でおなじみの実在の僧侶、三蔵法師)の舎利(遺骨)を納めている。
また法相宗は2つ大本山があり、もう1つは興福寺である。
森村さんの説明が面白い。
薬師寺の塔は、一番高い「東寺の五重塔」や、一番古い「法隆寺の五重塔」のように、データによるはっきりした一番がないのですが、薬師寺のお坊さんは「日本で一番美しいのが薬師寺の塔です」というそうである。
やっぱり「一番」と回答できるのは誇りだし、言われたほうも記憶に残りますよね。
「金堂」では、
「花会式」(はなえしき)修二会(しゅにえ)とよばれる薬師寺で一番大きな行事が行われている最中で、法要が執り行われていました。
修ニ会とは奈良の大寺が国家の繁栄と五穀豊穣、万民豊楽などを祈る春の行事だそうです。
900年以前、時の堀河天皇が工房の病気平癒を薬師如来に祈り、霊験を得て回復した御礼として、三尊に造花を供えたのが「花会式」のはじまりとされています。
金堂前に設置されたスピーカーから、
朗々と力強く「薬師悔過法要」のお経をあげる声が流れている。
「金堂」の中を見れば、10名のお坊さんが声をあわせてお経をあげている。
時に大きく声をはりあげたり、節回しに変化のある独特の読経で迫力満点である。
ご本尊には、10種1700本の手作りの造花が宝物が供えられていて、にぎにぎしく色鮮やかである。
花弁は和紙を使い薬効効果のある草木で染色するなど、寺にゆかりの深い農家で、昔ながらの方法で丁寧に作られるそうです。
梅、桃桜、山吹、椿、牡丹、藤、百合、杜若、菊の造花はどれも精緻で生花の美しさや生命感を表現しつつ、薬師如来の須弥壇(しゃみだん)の荘厳具として、王朝の雅を表現しています。
その鮮やかな色を見て、ふとタイのロイカトンのお祭りを思い出してしまった。
そして「大宝蔵殿」では特別公開が行われていたので、母と二人で鑑賞することに。
奈良時代のお坊さんの筆による般若心教などの書が展示されているのだけれど、その字がとても力強く美しい。
しかも、当時は皆巻紙のまま"立ったまま〟書いていたそうなので、驚きである。
さて、薬師寺の次は、「東大寺」へと移動した。
桜の季節もあり、市中へ向かう道はとても混んでいる。
車の中で母の修学旅行の話しを聴いた。
母が、就学旅行で京都、奈良、伊勢を訪れた60年前は、戦後の物資の少ない時期で、
学生はそれぞれみな決められた量のお米を持って出かけたそうだ。
14日間という初めての長期旅行の準備で荷物がかさんでしまい、
母は両親から赤い金属製のトランクを買ってもらい、その中に着替えとお米を詰めたらしい。
かなり昔のことゆえ、すっかり奈良の旅の詳細は思い出せないらしいが、
「若草山」近くの旅館に泊まり、皆で手を繋いで若草山に昇ったことを今でも憶えているそうだ。
現存する最大規模の木造建築の「東大寺」
伽藍(がらん)を進んでいくと、金堂の周辺は外人観光客も多く、かなり混雑している。
大仏殿の金堂に近づくにつれ、その大きさに圧倒される。
焼失のための過去の建て替えの度ごとに規模が小さくなっているとはいえ、とてつもない大きさである。
後ろにいる外国人の "So beautiful...."と感嘆をもらす声が聞こえてきたが、まさに同感。
奈良のお寺では、京都と違い写真のように「灯明」が必ず中央に存在する。
京都は左右に灯明があるそうだ。
奈良では仏様を照らすという意味で、中央に置くことになっているらしい。
巨大な「奈良の大仏」片方の手には大人が9人くらい乗れるとのこと。
大仏の右にある「多聞天」
二月堂に向かう途中、鹿におせんべいをあげたら、
ワラワラとよってきて、ちょっと怖かった...
東大寺の「二月堂」京都の清水寺と同じ作りになっている。
奈良公園の「鷲池の浮見堂」桜が咲いていて風雅な感じ
猿沢池から「興福寺の五重塔」を眺める
3日間、本当に楽しい旅でした。
by bandoh
旅行 : 12:22 : comments (x) : trackback (x)
2010-04-07 Wed
内宮参拝を無事終えて神宮会館に戻り、皆でのんびりと朝食をとることにした。
食いしん坊の母は、私よりも朝はしっかりと食べる。
食べないとイライラするらしい。
娘である私は、逆に朝沢山食べてしまうと、調子が悪くなってしまう。
嬉しそうに朝食を食べる母を見ながら、Y女史が感心して
「お母様、本当に明るいエネルギーで、開けていて素晴らしいわぁ~」と褒めたので、
76歳の母は、嬉しそうに「そうですか、、ウフフ」と顔をほころばせて上機嫌。
母は年を重ねるごとに、かつての"鬼のような気迫と威厳"は影をひそめ、何だか天然で可愛らしい感じになってきている。
これからも、可愛い系のおばあちゃんに、ますますなっていくのだろうと思う。
(時々、その天然ぶりを発揮して、娘も孫も、ヒェ!っと引くようなことを、のたまうのですが...)
(大体、母は数年前まで、銀行に定期預金というものがあることを知らなかった人である)
そんなことを考えながら、時計を見ると、まだ午前9時である。
あれだけお参りしたのに、まだこんな時間とは...、
"早起きは三文の徳"というけれど、ホント1日を有効活用できて素晴らしい。
朝食を終えて、会館をチェックアウトした私たちは"志摩"に向けて出発
途中F女の提案で、五十鈴川で車を停めた。
川にかかる浦田橋の上から眺めると、両側の土手には延々と桜が続いている。
橋のたもとで咲いている桜は山桜である。あまりに可愛いので写真を撮ってしまった。
伊勢志摩スカイラインを30分ほど走ると、「伊勢志摩国立公園」に到着した。
Y女史は、英虞湾を上から眺める景色を、是非私たちに見せたいと思い、ここを選んでくれたそうだ。
早速、「横山展望台」に昇ってみると、すごい。
眼下に英虞湾の複雑に入り組んだリアス式海岸と沢山の島、水平線が広がっている。
今まで見たことがない景色なので、母と二人で「すご~い!」と歓声をあげてしまった。
まるでラグーンが数多く点在しているようにも見える。
坐骨神経痛が持病の母は、こういうときに案外驚くほど元気。
痛いとは決して言わずに、元気に皆についてセッセと歩く。
高いところに昇る話しは、炎天下でない限り、今まで断ったためしがない。
F女とT女史は、一段高いところから景色に見入っていたが、
F女は「景色は変わらないから、昇ってこなくても大丈夫」と無駄足を運ばせないようコメントを伝えてくれる。
母の足を考えてのコメントだろう、やはり気配りの人である。
さて、私たちは国立公園を後にして山を下り、展望台から見下ろしていたであろう場所へと移動した。
志摩随一のホテルである「志摩観光ホテル」へ立ち寄る。ホテル好き
写真は、志摩観光ホテル・クラッシック(つまり旧館)のアプローチです。
この辺りの桜は、咲くのが早いようで、私たちが行ったときには、見ごろを終えてすでに大部分の花は散っていた。
想像したとおり、ホテルの庭からの眺めは素晴らしく、ウネウネと青く伸びたリアス式海岸が見える。
プライベートビーチの上に立つ別荘から景色を眺めているような静けさがある。
景色が見えるホテルのロビーで、お茶を飲みながら本でも読んで小1時間は過ごしたい場所である。
名ホテル&抜群の景色となれば、
皆で記念写真を撮りたくなるものである。
ホテルの内部のインテリアは古く、子供の頃に泊まったホテルの調度を思い出させる。
そう、70年代調の格式あるホテルが、綺麗にメンテナンスされ、使われている感じである。
無駄な装飾がなくシンプルで、色使いが少なくコントラストは弱め、インテリアはセクシーじゃないけど品がある。
メインダイニングのレストランをチラリとみると、格式を感じさせる雰囲気がある。
昔の「箱根プリンス」のレストランにちょっと趣が近い。
さて、クラッシックに続いて、次は、少し離れた場所にある
「志摩観光ホテルベイコート」へと移動。
ホームパージを見て、泊まるならばベイコートにしようと私は思っていた。
エントランスから入ると、水に浮かぶバラが出迎えてくれる。
フロントの天井から下がり、ホールを照らすライト
蜂の巣のような金属の線で造られたオブジェについているプツプツしたものは、全て英虞湾で採れた真珠だそうだ。
小規模高質なホテルのサービスを思わせるラウンジは小ぶりで、居心地が良い。
クラッシックとの比較でいえば、ベイコートは、モダンにアジアンが加味された感じ。
色使いは、ベーシックな茶系でまとめられ、さし色のブルーとオレンジが効いていてエネルギーを感じる。
中庭のプールだけ見ていたら、アジアのリゾートホテルかと思ってしまう。
でもプールの側にバーがないのは、艶消しで、ちょっと面白みがないなぁ....。
そうこうする内にランチ
Y女史の推薦で予約していた「プライムリゾート賢島」へと向かう。
ここは、オレンジ色の瓦屋根に白い壁を持つ、南欧風のリゾートホテル。
ここからも美しい英虞湾の海が見下ろすことができます。
ホテルの窓からからみえる景色でいえば、志摩観光ホテルよりも、こちらのリゾートの方が開放的な感じがします。
特にホテルのレストラン、"アッシュ・ドール"からは湾の景色が綺麗に広がって見えます。
スタッフの方々が、私たちのテーブルをセットしてくれています。
5人でアッシュ・ドールの座席に座ったところで、記念撮影。
しかし、海辺の日差しは暑い。
ジリジリと照りつける日差しを浴びて、着ている服を脱ぎ捨てたくなってしまった。
朝寒いかなぁと思い、タートルネックを着たことを後悔してしまう。
コースの一皿目は
ココット入り半熟卵 小エビとシャンピニオンのクリームソース
そしてレンズ豆のスープ うなぎスモークの浮身
サーモンのポワレ オゼイユ添え シブレット・ソース
そして、骨付きポーク 背肉のソテープラム添え
お腹がかなり一杯になったところで、
デザートは、クレメ・ダンジュ
ちょっと食べすぎたかな、、、。
私よりしっかりと朝食べていた母も、ポークは残してしまった。
ボリュームのあったランチの後、
コーヒーを飲みながら、私たちはややまったりとしてしまった。
しかし、ここでY女史、F女、T女の3人が、
「お母様、お肌がとっても綺麗、とっても70歳を超えているなんて思えない」
「お若いわ~。それにとっても明るくって素晴らしい!」
「髪の毛もきれいな白で、フサフサしているしねぇ」
と口々に褒めそやすので、母はまったりなんかせずに、すっかり嬉しそうにはしゃいでいる。
娘の目からは、今の母は様々な責任からすっかり開放されて
自由に人生を謳歌しているようにみえる。
私もいつかこんな風に、老後を迎える日がくるのだろうか?
こんなに明るく76歳を迎えることができるのだろうか?
そうなりたいと願う。
ともかく、ちょっと難儀な面も時々ありますが、元気で明るく楽しい母は最高です。
そして夕方が近づいてくる頃、私たちは志摩を後にし、
鳥羽へと向かった。
今晩は、予約していたエクシブ鳥羽に泊まる予定。
しかし志摩から鳥羽に向かうルートが渋い。
ナビが示す最短距離のルートなんだろうけれど、農道とか林道のように細く、しかも曲がりくねっている。
対向車がきた場合、私だったら絶対に通り抜けできないに違いない。
1つの車で命をかけた?運命共同体の5人は、固唾を呑みながら、この"獣道"が早く終わることを祈りつつ、緊張感を紛らすためにジョークを飛ばす。
果てしなく続く"獣道"を、Y女史が果敢に通り抜け、やっと表通りに出ると、すぐにエクシブが見えてきた。
無事宿泊場所に到着。ホッ
しかし、ホっとしたのもつかの間、車を停めてホテルのロビーに入ると、ものすごい人でごった返している。
老若男女、お子様から学生さん、ご夫婦、おじいちゃま、おばあちゃまたちで、ロビーはすごいことになっている。
今までの志摩観光ホテルやプライムリゾート賢島の静けさとは対照的である。
(まぁ、メンバーシップを持っているホテルの経営が上手く行っていると思えばいいのでしょうけれど)
ともかくも、喧騒を抜けるようにサッサと部屋にチェックインし、少し休んで温泉につかることにした。
エクシブのお部屋からも、海が見える。
今度は鳥羽の海である。
母と二人、しばらくベッドで横になって休んだ後、
人の少ないであろう夕方5時以降を狙って、スパにいったが、やや混み状態である。
あ~
「名湯」といわれているのがうなずける感じがした。
温泉から上がって、しばらくすると、部屋の電話がなり、
寿司会席の席があいたという連絡が入った。
母と二人着替えて連れ立ち、イソイソとレストランへと降りていく。
カウンターに座ってメニューを開き、すぐに「伊勢海老の会席」を食べることに決めた。
魚介は全て地のものであるらしい。
付き出し1
ホタルイカの酢味噌
付き出し2
エビと竹の子
こうなるとキリっと冷えた冷酒が飲みたくなってくる..
辛口の義左衛門(ぎざえもん)純米吟醸をお願いする。
季節のお吸いもの
季節のお作り
お薦めのさざえの壺焼き
煮物
伊勢海老の具足煮
そして、その後は「握り」を9種類
伊勢海老からスタートして、トロ以外のネタは、全て地のものだそうだ。
本当に小さく「シャリ小」にお願いして握って貰っているので、ちょっとバランス悪くネタがよれて写っていますが、
とっても美味しかったです。
タコ、タチウオもいけてました。
(美味しいと写真忘れます)
伊勢海老の赤だし
これ意外な感じがしました。白味噌のイメージが出来上がっているんだと思います。
ちなみに、全国のエクシブの中でも、お鮨を出しているのは鳥羽だけだそうです。
板前さんの感じがよくて、サービスも料理もとてもよい感じです。
もっと増えるといいのに。
美味しいものを食べているときは、人間誰でも幸せである。
「伊勢、志摩、鳥羽っていいところねぇ...」
と母と二人で、幸せ気分にひたりながら、夜は更けていく....。
明日は、遷都1300年の奈良へ
by bandoh
旅行 : 00:00 : comments (x) : trackback (x)
2010-04-06 Tue
翌朝、目が覚めるとまだ薄暗い...。
畳の匂いと、木の天井で神宮会館であることを思い出す。
今日の内宮参拝を考えるとワクワクしてきた。
いつもより元気よく起きて準備を整えて、いざ出発しようと靴を履いている最中に母が部屋の扉をノックした。
グッド・タイミングである。
表に出ると、空は青く澄み渡り、薄蒼いピンク色の桜の花が、目に眩しく飛び込んでくる。
まず内宮参拝の前に「猿田彦神社」へお参りにいく。
猿田彦大神は、天照大御神の孫、ニニギ尊(ニニギノミコト)が、神々の国である高天原(たかまがはら)から宮崎県の日向(ひゅうが)の高千穂に向かう際、猿田彦大神がその道案内をしたことから、道や境界を守る神様、方位の神様として信仰を集めるようになったそうだ。
これから何か始めようとするときや、今後の方向性に迷っている人など、ここで参拝すれば道が開けると言われている。
道案内ということで、参拝の前に参っておくとよい神社なのだと思う。
そして、次は皇大神宮別宮の「月讀宮」を参拝
こちらは天照大神、須佐之男命と合わせて三貴神とされる、「月讀尊」をお祀りしてあり、月讀尊は天照大御神の弟神となります。
早朝の参道はすがすがしく、冷たい空気も心地よく感じられます。
原生林のように自然の姿を残して茂る樹木が、キシキシと玉砂利を踏み進む私たちを静かに見守っているように感じるから不思議。
奥に進んでいくと、四宮が並んで南を向いてお祀りされています。
ご兄弟の順に参拝するというY女史に従い、向かって一番左から「伊佐奈弥宮」、「伊佐奈岐宮」、「月讀宮」、「月讀荒御魂宮」の順にお参りをしました。
月讀宮は、月を奉るお宮なのだそうだ。
月は、太陽と地球のバランスを取っていて、月がないと地球は自転が2/3も速くなって大変なことになるらしい。
太陽は男性性、月は女性性をあらわすが、そういう意味では、バランスを取る神様なのです。
2つのお宮を参拝した後は内宮へ。
宇治橋につくと、檜で作られた橋が朝日の中で燦然と輝いています。
五十鈴川の上にかかる、あまりにも美しい宇治橋に感動。
こんなにミニマムに優雅で美しい橋をかつて見たことがあるだろうか...。
宇治橋の中央線はやや高くなっていますが、
冬至の日の太陽は、ちょうどこの中央線の延長線上に昇るそうです。
最初に宇治橋を作った人たちは、すごい。
橋の両端には二つの大鳥居がありますが、これらは内宮、外宮の旧御正殿(きゅうごしょうでん)の棟持柱(むなもちばしら)をリサイクルしたものだそうです。
さらに二十年経つと他の土地の鳥居に、さらにそのあとも他の神社へと、どんどんリサイクルされていくのだそうです。
大鳥居をくぐって、参道を進むと、青く広がる空と満開の桜と松が見えてきます。
南から放射状に走る雲が、「特別参拝」に向かう静粛な気持ちに高揚感をプラスしてくれる。
そう、今日は昨日から申し込んでおいたので、内宮の「御正宮」で一歩内部に入って参拝できることになっている。
第一の鳥居をくぐって参道をしばらく進むと、右手に石畳が広がり、五十鈴川の御手洗場へと下りていけます
更に進むと、参道は深い森に包まれ、静かで神々しい雰囲気に包まれます。
それと同時に空気もヒンヤリとしてきます。
五十鈴川の後は、そのまま表参道に戻り御正宮に向かうルートが一般的なようですが、
「滝祭神」で参拝。
滝祭神は、五十鈴川を守る神様をお祀りしている重要な神社です。
竜神様への参拝の後は、そのまま森の中を進み、しばらく歩くと、新しくかけられた鳥居と橋が見えてきます。
風日祈宮橋(かざひのみのみやばし)の鳥居です。
新しい橋と並んで、古い橋はカバーがかけられていたので、建替え工事をしているのか?
風日祈宮橋を渡ると風の神様の「風日祈宮」です。
風日祈宮には、外宮の「風宮」と同じく、風の神様がお祀りされています。
「風日祈」とは、風雨の災害のないようにとお祈りする神事のことを言うそうです。
内宮の開運の鈴のお守りと、天照大神の御札を受け取った後、神楽殿を左に見ながら進む。
いよいよ、伊勢神宮・内宮 御正宮参拝です。
神楽殿を過ぎたら、表参道を歩き、「御正宮」に向かいます。
三十段あまりの石段の上を見上げると御正宮が見えます。
そして、写真のとおり石段はゆるくカーブしていますが、これは、真正面から神様に近づくのを避けるために、わざと造られているようです。
石段を昇り切ったら、一番外側の「板垣南御門」をくぐります。
太陽の神、天照大御神がお祀りされている伊勢神宮・内宮の「御正殿」は、四重の垣根に囲まれた一番奥にあります。
一般の参拝者は、外玉垣甫御門(とのたまがきみなみごもん)の前までしか入れませんが、
今回は特別参拝を申し込んでいたので、外玉垣甫御門にかかる白絹の御幌の向うの
御垣内(みかきうち)と呼ばれる清浄な神域に入って、特別参拝を行いました。
申し込んだ5人で、御門横の南宿衛屋にいる神職さんに「特別参宮章」を出した後、
まずはコートを脱ぎ、一列に並んで神職さんからお祓いを受けます。
そして、そのまま神職さんに続いて、御垣内の外側の番塀から、御垣内に入って、中重鳥居の前まで進みます。
しかし、御垣内の玉じゃりが、何とも大きなサイズの石で、うっかり踏み損なうとバランスを崩して転びそうな感じで、ややヨロヨロしながら進みます。
こんな神聖な場所でころんで、ずっこけたくない。
私が代表者として、「中重鳥居」の側で参拝させて頂いたのですが、
二拝二拍手一拝の最後の拝が、かなり長かったようで、神職さんがタイミングを合わし損ねていたそう。
はい.....ついついここでもお願いごとを。(知らぬということは恐ろしい)
母から後で「長すぎ」とチクリと言われました。
特別参拝の申し込みの際に、第六十二回神宮式年遷宮への奉賛として、御造営資金をご奉納しました。
御正宮でのお参りを終えたら、伊勢神宮・内宮第一の別宮
「荒祭宮(あらまつりのみや)」へ
ここは、天照大御神(あまてらすおおみかみ)の荒御魂をお祀りしています。
荒御魂(あらみたま)は、昔から困ったことや願い事があると、この別宮に頼ってきたと言います。
新しい仕事に着手するときや、困ったことが起きて先に進めなくなったときなどに、荒祭宮にお参りするとよいとされています。
そして、最後に再び宇治橋へ。
新しい宇治橋を桜の満開の時期に見れるとは、なんと幸運なのか。
もともと桜の季節を狙ったわけでは無かったので、この機会を下さった神様に心より感謝の念が湧いてきてしまった。
「神様、本当にありがとうございます」
母も道々、「桜がホント綺麗だわ~、いい時期にお参りできたわ~」
喜んでいるので、宇治橋でのポーズも決まっている?
しかし、この幸運、考えてみたら、
あれこれと人が喜ぶために気を配るF女の日ごろの行いが宜しいのかもしれません。
となると、「ちもちゃん、どうもありがとう!」と再度感謝の言葉を伝えたい。
朝8時頃に参拝を終えた私たちは、そのまま神宮会館に戻り、朝食をしっかりと頂きました。
さて、伊勢神宮参拝の後は、志摩と賢島へ向かいます。
by bandoh
旅行 : 23:23 : comments (x) : trackback (x)
2010-04-06 Tue
自宅前の桜がようやく満開となった朝早く、伊勢神宮に向けて出発。
写真は無事伊勢につき、外宮の手水舎で心身を清めている母と私たち一行
母から以前より「フミちゃん、連れて行って!」と何度かリクエストのあった"お伊勢参り"の旅である。
私の周りには、ここ数年、伊勢神宮にお参りをしている人が沢山いる。
本格的な人は、滝打たれの行のような禊ぎをしてから、お参りをしている。
うちの旦那さんも、伊勢神宮には仕事の出張も兼ねて、何度かお参りをしている。
戻ってきてから「いや~、良かったよ~」とやや自慢げに語るので、私の中では、"お伊勢参り"は、ミステリアスかつ「絶対に行くべき場所」として刷り込まれてきた。
しかもお参りしてきた人たちの話しを聞くにつけ「それなりに本格的に参らねば....」という思いも強くなっていった。
「本格的に参る」と、
神事にはとんと疎い私が行くと決めたなら、それなりに本格的に参るために、"しかるべき人"に案内をお願いしなくてはならない。
ありがたいことに、近しい人の中に"しかるべき人"がいるものである。
私がソニーミュージックエンタテインメントに営業をしていた15年前頃から、当時は教育の担当者として、今はうちの会社の仕事を手伝って貰ったり、ご飯を一緒に食べる相手として付き合いの長い、しっかりもののF女に案内を願いでた。
F女は、神社と関係のある家系から神事に明るい。
F女は、私が「今度伊勢に行こうと思っているのよ」とつぶやくと、
「大丈夫。バンちゃんが伊勢に行く時には、それなりの人を紹介するから」と頼もしい笑みと共に引き受けてくれた。
あまり多くを語らずとも、本当に親切になんでもかなえてくれるスーパーウーマンである。
おかげさまで、神事に疎くせっかちな娘と、やや天然な母の親子連れは、めでたく旅に向けて出発。
しかし、旅の1日目となる朝、東京駅につくと、強風のため、東海道新幹線の運行が遅れているというアナウンス。
どうなることかと思ったが、数分遅れで無事名古屋駅に到着し、予約していた近鉄特急に無事乗り換えることができた。
危惧していた朝からの雨もあがり、お参りに傘を差す必要もなさそうで、ホっとする。
もっとも、私の心配をよそにF女は朝から余裕たっぷりで、
「大丈夫よ、バンちゃんとの旅で雨にあたったことなんて無いじゃない」と全く心配していないから、この人はすごいと思う。
伊勢駅で、F女が親しいY女史とT女史の二人と落ち合い、まずはY女史が運転する車に5人乗り込み、外宮へと向かう。
Y女史は今は関東に住んでいるが、志摩に長らく住んだことがあり、F女と同じく家系的に神事に明るいし、日本書紀なども勉強していて詳しい。
Y女史は、私の知らない世界を紹介して頂ける、大事な水先案内人兼先生でもある。
外宮の北参道の駐車場につくと、Y女史はなぜか駐車スペースの一角の中にまっすぐ停めず、対角線となるような形で、車を斜めにパークした。
「もしかして、これも何か意味があるのかもしれない」と密かに思ったりしたが、毎回そんな風なので単に停め直すのが面倒らしいと判明した。
Y女史はいたって大らかな性格で優雅な感じがするが、経営者としての貫禄もある。
すごいわ~と関心するだけでなく、この駐車のエピソードによって、Y女史にはすっかり親近感を感じてしまった。
これは、外宮の御池の近くにある超パワースポット、「三つ石」
ここでお参りの前に手を合わせた。
そして、いよいよ神様がいらっしゃる「御正宮」
御正宮は、四重の垣に囲まれている。
一般の人の参拝は、一番外側の御門をくぐり、外側から二番目の御門まで。
その二番目の御門となる「外玉垣南御門」
純白の絹の御幌(みとばり)ごしに参拝します。
次に参拝するのは、風の神様の「風の宮」
鎌倉時代に神様が力をあわせて神風をふかし、モンゴル軍の襲来から日本を守られたといわれています。
次に参拝するのは荒御魂(あらみたま)を祀る「多賀宮(たかのみや)」
多賀宮には、外宮のご祭神、豊受大御神の「荒御魂」をお祀りしています。
個人的なお願いごとは、ここで初めてできるそうです。
そのようなことも知らなかった私は、ずっとお願いごとを重ねていて、
荒御魂は、願いごとに対してパワーを与えてくれる神様なのです。
ちなみに、神様の魂には
・穏やかで優しい和御魂(にぎみたま)
・行動的で激しい荒御魂(あらみたま)
があるそうで、外宮では和御魂を「御正宮」に、荒御魂を「多賀宮」に分けてお祀りしているそうです。
次は土地の神様である別宮の「土宮」(つちのみや)に参拝
ここに祀られているのは、土地の守り神の大土乃御祖神(おおつちのみおやのかみ)です。
土地にまつわるようなこと、引越しとか不動産の売買など考えている人は参拝すべき神様です。
外宮の参拝を終えて、この日泊まる「神宮会館」に全員でチェックイン。
神宮会館は、内宮とおかげ横丁のすぐ側にあり、とっても便利な宿泊施設です。
ただし、予約が早くから入ってしまうので、新館に予約を入れたい場合には、早めの予約が必要。
この日は、4日(日)の奉納相撲があるので、神宮会館の入り口に書かれた予約名を見ると、相撲部屋の親方一行も宿泊している。
荷物を預け、母と私はいそいそと「おかげ横丁」へと向かい、
薦められた「赤福本店」でお茶と赤福で一服。
母と二人火鉢にあたりながら、店内に座って見ていると、次から次へと観光客が来ては出て行く。
みな滞在時間が短いので、回転数がすごい。
ふと帰り際に、赤福を作っている現場をみると、
若いお嬢さんたちが、赤福をせっせと作っている。
その手際の良さは、早廻しのビデオを見ているようである。
通りに出ると、赤福を食べたばかりなのに、またまた食欲をそそる、貝が焼ける香ばしい匂いが漂ってくる。
その匂いに釣られて近づいてみると、牡蠣である。
この後、少ししたらフレンチの夕食を食べる予定なので、食べ過ぎてもどうかと...と迷いつつ、
旦那さんから通称"ラッコちゃん"といわれている貝好きの私である、
やっぱり牡蠣も大アサリも食べることに。
神宮会館に戻って一休みした後は、
予約を入れてもらったフレンチ・レストラン、"ヴォン・ヴィヴァン"で夕食
郵便局の古い建物の中にあるレストランで、クラッシックで落ち着いた雰囲気のお店
そういえば、東京にも80年代に"ロアラブッシュ"というフレンチがオープンしたけれど、ちょっと似ている。
母は神都ビール、私はワインで乾杯
アミューズが可愛く、特に松坂牛が美味しい。
かぼちゃのスープ、
前菜の魚介のサラダ、
メインの松坂肉のみすじ肉といちぼ肉を食べた後は、デザート
私はフランボアーズ以外全ての種類をトライ。
本当にちょうど良いボリュームで美味しかった。
夜も更けて、非日常の刺激的な一日が過ぎさろうとしているが、
この夜、私は伊勢に来ているという実感がまだ湧いていない気がした。
多分、あれやこれやと物珍しく、キョロキョロしていたせいで、地に足がついていなかったのかもしれない。
この感覚は、ローマに行ったときにもあった。否、過去の旅行でも初日はいつもそんな感じのように思える。
伊勢参りをした昔の江戸に住む人たちが、遠く長い道のりを、何日も歩いて到着するのと違い、
今日、伊勢参りをする私たちは、東京からほんの数時間もかければ、すぐに伊勢についてしまう。
物理的に長い距離を移動してきたわりには、鉄道や飛行機という便利な交通機関があるせいで、早く現地についてしまい、頭では遠くにきていると理解していても、体の細胞は遠くに来たということを認識できないでいるのかもしれない。
ともかく、神々の御霊が鎮座している伊勢の地と空気に早く溶け込もうと、神宮会館の布団の中でスっと目を閉じた。
明日は、早朝6時30分に出発である。
by bandoh
旅行 : 18:26 : comments (x) : trackback (x)
2010-04-01 Thu
先週の土曜日27日に自宅で毎年恒例になりつつあるお花見パーティを開いた。
明るいうちからシャンパンで乾杯
桜よ咲け~と、随分前から念じていたのだけれど、お花見の週は始めこそ暖かかったものの、半ばから急に寒くなり、遅咲きの自宅前の桜は残念ながらチラホラとしか咲かず、残念
ただ正直な話し、毎年、ゲストはやってきても、誰も桜の木を眺めることはなく、桜が満開でなくとも支障はない。
「花より団子」と言うべきなのか、皆、楽しく飲んで食べてしゃべって過ごしている。
今年はお誘いをかけたところ、30名を超える人数となり、狭い我が家にギューギューの状態となってしまった。
途中でお断りをしてしまった方、本当に今年は申し訳ありませんでした。
(もしかしたら、あと5名くらいは入ったかもしれない...と反省)
お料理は、時間ごとにテーブルが空いたら、次の料理を作り置いていく。
(長時間に渡って、美味しいお料理を作ってくれる、友人中島&小笹シェフ、そして洲崎、赤井さんに大感謝!)
ちょっと人数が増えたこともあり、簡単に最近の近況報告と自己紹介
夜もふけてゲストの数も増え、外は寒いが室内温度は上昇
楽しい一日は、あっという間に過ぎ去りましたが、
途中でベッドルームに引きこもった失礼をここでお詫び致します!
来年は途中「仮眠」せずに、パーティの全貌を見届けることに専念するつもり。
また、来年も皆様ぜひご参加を!
by bandoh
イベント、観劇 : 19:17 : comments (x) : trackback (x)
レストラン、ショップ : 14:47 : comments (x) : trackback (x)
2010-03-04 Thu
「ホントーに、ものすご~く気を使っているんですよ」と、仲の良い某外資系の企業の「女性部長」のA子が、ゆるくウェーブのかかったセミロングの髪の毛を掻きあげつつ、実感のこもった声で断言した。
この日は、女性3人で最近転職したA子の近況の話しを聴くために、一緒に夕食を取ることにしたのだった。
3人が揃ったところで、いつものごとく泡物(シャンパン)で乾杯した。
A子は、知人の紹介で今の会社に転職することになり、新たな会社で働きだしてから、まだ日も浅い。
もう一人の友人B子も、業種は違うが同じく外資系企業で働く「女性部長」である。
A子もB子も、男性以上に気が強く、バリバリ働くキャリア・ウーマンである。
今後の自分の身の振り方を考えているB子にとって、A子の転職の話しは関心の高いテーマである。
40歳を超えてからの転職は、ある意味でハードルが高い。
慣れ親しんだ職場から(偉そうな態度が取れる?)、自分を知っている人が誰もいない環境に飛び込むのだから、本来の自分を知ってもらい周りからの信頼を得ることはなかなか大変なことである。
しかも、部長という役職を担っての転職であれば、当然それなりの実績を期待されての入社であるからプレッシャーも高い。
クライアント先の企業で、中途入社の管理職の人について
「あの人、本当に無能で仕事ができない。なんであんな人を採用したのか」などという話しを時々耳にすることがある。
実際に実務ができないのか、それとも新しい環境の中で、職場の人の信頼を勝ち取るコミュニケーション力が低いのか、理由はよく分からないが、中途入社の管理職で、ポジションに応じた信頼を得ていない人は、少なくないと感じてしまう。
個人的には、そういう信頼を得られない人たちは、総じて社内の意見や空気を読むのが苦手な方々であると感じる。
敵にしてはいけない人を敵にしていたりと、社内力学についての嗅覚が弱いとも言える。
その点で言うと、A子の話しは面白いと思った。
「バンドーさん、私が誰に一番気をつかっているかって言うと、セクレタリーやアシスタントの女性達なんですよ」A子
「分かる、女だから分かるけど、女性って怖いからねぇ」私
「彼女たちを敵にするなんて、とんでもないですよ。み~んな、つぶさに人のことよく見てますからねぇ。瞬時にして、服装、化粧、バッグに至るまで何を持っているか確認して値踏みしてるし、鋭い観察眼でこちらがどれ位の人間なのか、男性なんかよりもず~っと冷静な目で判断してますよ」A子
「そう、そう」
「何か下手なことをしたり言ったりしたら、瞬く間に彼女たちの女性口コミネットワーク網で社内に広がりますからねぇ。しかも、セクレタリーに嫌われたりしたら、大変。何気ない風を装いながら、彼女たちって自分の上司に“○○さん、こんなこと言ってましたよ”なんて、こちらが不利になるようなこと言ったりするじゃないですか」
「それってある。それで役職を追われた人、実際にいますよ」B子
「男性の嫉妬も嫌だけど、女性を敵にするって、もっと怖いと思いません?」A子
「そう思う!」とA子の熱気にやや押されながら、私もB子も揃ってうなづいてしまった。
「だから、私、ホントーに今涙ぐましいほど、ワンダウンポジッションを取って努力してるんですよ。実は社内に一人、あっこの人、敵に回したら怖いっていう女性がいて、もうそういうの嗅覚っていうのか、臭いで分かるんですけど、ものすごく気を使って、荷物運ぶのが見えたら手伝ったりして。でも、彼女案の定、キーパーソンだったみたいで、彼女が何人かに私のことをよく言ってくれているみたいで、知らない部門の人との折衝がやりやすくなったんですよねぇ」
とA子は自分にしかと言い聞かせるように話すと、それに呼応するようにB子も、
「分かる~、私も、自分のアシスタントの女性に対しては特別な配慮をしたりしてますよ。周りの昇給ができないときでも、彼女の昇給分だけはしっかり確保したりして。だって、彼女達に反旗を翻されたら、自分の足場が揺らぐし、彼女達って社内の情報を持ってますからねぇ」と話す。
そう言われてみると、確かに私自身も、ポジッションに関わらず同性である女性に対しては、男性以上に気を使っている。
女性は、女性の怖さをよく知っているからなのだろうか?
冷静に見て、A子もB子も、日本の企業で働く女性の中では、ほんの一握りにあたる部長という肩書きを持っているが、決して女性に嫌われることなく、むしろ味方につけていると思う。(もしかしたら男性に敵がいるかもしれないが)
また、二人とも新しいプロジェクトを推進していく能力が非常に高い。
もしかして、社内で出世していくためには、女性を味方につけることが鍵なのだろうか...。
否、というよりも、専門能力に加えて、女性を味方につけられるほどの場読みと気配りができる能力があれば、仕事もできるということなのかもしれない。
男性の皆様、「女性アシスタントのパワーをあなどることなかれ」である。
by bandoh
徒然なるままに : 00:45 : comments (x) : trackback (x)
2010-02-21 Sun
久々に更新
12月からずっとこのブログを更新しないでいたので、何人かの友人からメールを頂いてしまった。
「どうしたの?大丈夫ですか?」
「最近更新していないので、気になっています」
と私の近況を心配している内容が多い。
実は1月に入って更新しようとしたところ、システムの不具合で単純に更新できなかったということもあり、それに加えて年初から研修が入っていて忙しく、なんとなく、その後書き込むタイミングを逃したまま、ずってきてしまっていたというのが原因である。
体調が悪いとかそんなことはなく、いたって元気である。
(ということで、この場を借りて、“心配をおかけした皆さん、私は元気です。”と改めてご挨拶を致します)
そのことをメールで返信すると、みな、
「それは良かった。安心しました。それにしてもこのご時世で、仕事が忙しいというのはいいことですね」
といった内容の返事を下さる。
“忙しいのはいいことですね”
確かに。
世相を反映しているというか、この不景気の寒~い風が吹く時代、忙しいということは良いことなのだろう。
私のような零細な組織にとっては、ありがたい話しである。
しかし、仕事で忙しいのはいいことだとは言え、仕事にかまけて体調を崩したりしては元も子もない。
「健康管理」は私にとっては重要なテーマである。
独立して仕事をしていると、病気は大敵である。
昨年12月に初島で群発地震に見舞われ、肝を冷やしながら、
自分の命と今後の健康管理についてツラツラ考えてみた。
自宅で行うストレッチ以外にも、何か体を動かすことが必要だろう...と。
最近周りの人間を見ると、ジョギング、走っている人が多い。
一緒に仕事をしている男性コンサルタントも走っている。
仲の良い男性の友人の一人は、毎日走っているそうだが、昨年になってそのジョギングに彼の妻が参加することになり、夫婦間の会話がグっと増えたそうだ。
また、ヨガを始めた友人もいる。
体にもいいし、気持ちがリラックスできるのでストレス発散にもなっていると言う。
昨年から、彼女が通うスタジオにニューヨークから男性のインストラクターが招かれて、クラスを教えているらしい。
また、そのインストラクターは誰もが見とれるかなりのイケメンで、彼の登場以来、クラスの人数が急激に増えたそうだ。
なかでも、オカマチャンらしき参加者の数がドっと膨れ上がっているとのこと。
ケーブルTVでアメリカの恋愛ドラマを見ていると、中高年に差しかかりつつある男女が、必ずといっていいほどジムでトレーニングをしている風景が出てくる。大体、俳優さんたちは、皆おしなべて、出るところは出て、引っ込むところは引っ込んでいる、Nice Bodyである。
私も、健康管理とシェイプアップを兼ねて、「何かやらなくては...」と、ようやく重い腰を起こした。
とはいえ、学生時代スポーツをしていたので、体を動かすことが嫌いなわけではないのだが、
走ることも、ジムに通うことも、あまり好きではない私。
走るのって苦しいし、ジムに通ってみんなで我慢大会みたいに苦しいエクササイズするのも好きではない。
筋トレも、単調で楽しくないので好きじゃない。
ヨガも、自宅でストレッチをしているので、何だか出かけてやるまでの意欲が湧かない。
ゴルフは、ずっと長いことやっているのだけれど、丸1日時間を取られるのと日に焼けるのが嫌で、5年ほど前からコンスタントには行かなくなっている。
う~ん...と初島でしばし考えた結果、やっぱりダンスかもしれないと思った。
今まで体を動かした中では、ダンスが一番楽しい。
そしてダンスをやるならば、やっぱり「アルゼンチン・タンゴ」が断然いい。
私がアルゼンチン・タンゴに興味を持ったのは、ずいぶん前に深夜のTVで「タンゴレッスン」という映画を観たことがきっかけだった。
モノクロの映像でどちらかといえば地味な感じの映画なのだが、強烈な印象が残った。
監督&主演は、サリー・ポッターという女性である。
とにかく、アルゼンチン・タンゴは踊っているときの動きが優雅で美しい。
TVでやっている社交ダンスは、じっと観ていると、あのピーンとそらした背筋と笑顔に、古臭いというか、田舎くさいというか、わざとらしいというか、観ていて、「あぁ、お願い、やめて~」とこちらが気恥ずかしくなってくるような感じなのだが(すみません!やっている方)、「タンゴ・レッスン」の中のアルゼンチン・タンゴにはそれがまったくない。
そもそも、アルゼンチン・タンゴでは、男性も女性も背筋そらしてピーンというのはないし、社交ダンスの中で踊られるラテンダンスのように、妙にクネクネした動きもない。
アルゼンチン・タンゴを踊っている女性の動きは、自然にしなやかで、特に脚の動きが軽やかで綺麗である。
映画を観ながら、「こんなに体の動きを、格好よく美しく見せるダンスがあったのか!」と見とれてしまった。
だから、映画の名中で、かなり年齢がいっている、思いっきりおばさん顔の主演のサリー・ポッター監督が、同じく主演俳優&タンゴダンサーのパブロ・ヴェロンと踊っているのだが、彼女の年齢を超えてとても美しくセクシーに見える。
(彼女の足が、ほっそりととても細くて綺麗というのもある)
また、抑えた感じでオーバーに感情を表現しないところも知的な感じがしていい。
その影響で、「私もいつかアルゼンチン・タンゴを習ってみたいわ~!」としっかり思っていた。
そこで、前に一度行った事のあるアルゼンチン・タンゴのスタジオへ行き、レッスンを始めることにした。
インストラクターは、アルゼンチン人のニコラス・ミアリ先生。
他のアルゼンチンの先生とはまったく異なり、かなり論理的な解釈の説明をしながら、ボディバランス、動きを教える人である。
タンゴ・レッスンのいい面は以下の3つであろう。
・いい感じの音楽を聴いて楽しく踊れる
・女性として優雅で美しい所作が身につく
・体を適度に動かすので、いい運動になるし苦しくない
<タンゴを踊る前にストレッチについて教えてくれる先生>
タンゴは“ペア・ダンス”である。
女性は、男性のリードに従って踊る。
踊りながら、相手と無言のコミュニケーション(意思疎通)を交わすことになる。
つまり、「曲のテンポや雰囲気」、「男性の腕の動きと方向」、「力の入れ具体(押しているか引いているか)」、「ステップと足の置き位置」にあわせて、女性は付いていくことになる。
付いていく=無言のフォロワーシップが必要となる
案外、最初はこれがペアダンスを踊る上での私の壁となった。
男性の動きにあわせて、ついつい先読みをしてしまい、コミュニケーションを間違える。
日常よく起こることが、ダンスでも起こるものである
大体、私は、仕事でも先回りして何でもやってしまうタチなので、先走りすぎる傾向がある。
案外、ダンスを習うことで、自分にとってはパートナーシップにおいて、マインド面のいい気づきとなった。
そして、スムースに美しく9センチ!という高いヒールで、安定して動くためには、
「キャットウォークでしなやかに歩く」、「上半身と下半身の動きにずれがある(上半身が先に動いて足が遅れてついてくる感じ)」、「常に体重は両足にではなく左右どちらかの足に乗っている」、「重心を低く保つ」、「上半身はそらずに肩と背中の力を抜き中心(コア)の筋肉を使う」ことが必要となる。
でも、これ全部、意識していると、頭の中がグチャグチャになってしまうときがある。
悲しいけれど、ビギナーは、先生のステップについていくのが精一杯で、1度に1つくらいしか意識できない、、、。
しかし、タンゴを習うことで、
アルゼンチン・タンゴを美しく踊れるようになり、
しかも健康とシェイプを維持し、フォロワーシップを学び、優雅な所作が身につくならば、先生のニコに、難しいこと言われても、ハードルの高いことを言われても、逆に俄然やる気になってきてる今日この頃である。
健康と女力アップ、今年も、楽しもう!
by bandoh
徒然なるままに : 11:24 : comments (x) : trackback (x)
2009-12-14 Mon
師走である。
この時期、私の場合も、会社の決算があったり、支払いが増えたり、来年度の提案があったりなど、何かと忙しくなってくる。
そう!忙しいんだけれども、、、、この時期、何だかゆるく楽しい気持ちになる。
(だって一歩街に出れば、クリスマスとお歳暮というギフト商戦のため、デパートをはじめどこの店も、クリスマスの楽しげなデコレーションと音楽で賑々しく飾り付けているんだもん)
だから、状況に反して「遊び心」と「ホリデー気分」が高まってくる。
それにこの時期、「忘年会」という、れっきとした言い訳があるので、「飲み会を企画せねば」という気持ちになり、どうせだから行ったことのないあの店に行ってみようなどと、浮き足だってしまう私は、やっぱり人と会ったり食べたりするのが好きである。
この時期は、銀座の街もいつも以上に華やかになり賑わしくなってくる。
毎年、ミキモト真珠のクリスマスツリーの前には人がたかる
ふとツリーのたもとに目をやると、
可愛い雪だるまのライトが、ほのぼのと立ち見客を歓迎している。
私は子供の頃、クリスマスが一年中で一番好きだった。
イベント好きの私の母は、クリスマス、お正月、節分、桃の節句、十五夜、誕生日など、祝ったり食事をしながら楽しむ機会を決して逃さない人である。
毎回、かなり気合を入れて、イベントを“決行”していたように思う。
私は子供の頃のクリスマス時期、
しまって置いたクリスツリーを箱から出して飾り付ける楽しさ、ツリーに赤と緑のライトがチカチカと点灯したときの嬉しさ、クリスマス曲のレコードを聴きながら食べたイブの食事と、クリスマスケーキの美味しさを、今でもしっかりと憶えている。
しかし何て言ったって一番嬉しかったのは、25日の朝である。
朝になると、母やおば達から贈られる沢山のプレゼントが、枕元に置かれていて、赤や緑や金・銀の鮮やかな包み紙とリボンが目に入るやいなや、「わぁ~
お菓子が入っているサンタのブーツも必ず毎年ついていたが、これを見るとクリスマス・ギフトっていう感じがして、妙に心を弾ませたものだ。
だから、まだ月日の感覚がしっかりとない子供の頃は、朝になり目が覚めると、母が家で掃除機をかける音が聞こえて、あぁ~まだクリスマスじゃないんだ、、、と、何度ガッカリしたことか。
大体、母のイベント好きは、母方の家系の特徴のように思う。
母の兄は、自分の誕生日にわざわざジャズのバンドを呼んで、パーティを開いていたし、
母の実家に行くと、なぜかいつも人が沢山いて、ワイワイとお酒を飲みながら御飯を食べていた記憶がある。
そう考えてみると、もしかしたら、私の「食事行かない?」とか「お花見やらない?」などと人を誘って食べたり飲んだりしたがる傾向は、母方の血のなせる業かもしれない。
そうならば、この師走の時期、キっと口を結び眉間に皺を寄せて、せっせと働く緊張モードに陥るものが、ゆるく「ホリデイ・宴会モード
さらにいえば、1歳上の私の従姉妹(母の兄の娘)もよく似ている。
大体連絡がくるときは、必ず「フミちゃん、何か美味しいもの食べにいかない?」である。
ラテンな家系?
それはともかくとしてもですが...、
私は「人生、何ていってもバランスが大事でしょう」と考えるタイプである。
いい仕事をして一生懸命働いて、家族や仲の良い友人と楽しい時間を過ごす、
だからこそ、人生を楽しく感じ、周りにも感謝の念が持てるのだと思う。
何事も「楽しむ」ことで、仕事も人間関係もより良いものになっていくと信じている。
今年も第3土曜日は初島に渡って、この一年を振り返り、来年に向けての展望を作る予定である。
楽しい仲間と楽しく、未来を見つめるための良い締めくくりとしたい!
by bandoh
徒然なるままに : 17:10 : comments (x) : trackback (x)